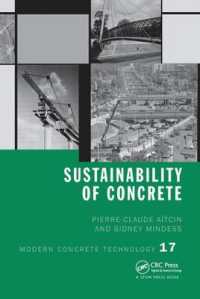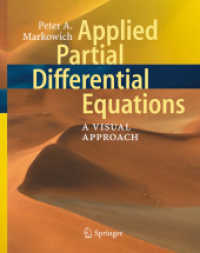出版社内容情報
読者の意識、社会の意識をつかむ文学を生んだ漱石の姿と近代化以後の日本の時代精神がいま明らかに。
内容説明
「…ともかく僕は百年計画だから構わない」。彼が期待した読みは果たしてなされてきたか。『こころ』の基礎である『文学論』から漱石の哲学を見抜く。読者の意識、社会集団の意識をつかむ文学がその時代の精神を表す。“政治体制編”『坊っちゃん』、“倫理思想編”『こころ』、大江健三郎『水死』まで―漱石の遺言に初めて答える。
目次
第1章 『坊っちゃん』の諷刺
第2章 明治の知の連環
第3章 ロンドンでの構想
第4章 文学は時代精神の表れ
第5章 エゴイストの恋
第6章 私を意識する私はどこに
第7章 『こころ』の読まれ方
著者等紹介
赤木昭夫[アカギアキオ]
1932年生まれ。東京大学文学部卒。コロンビア大学ジャーナリズム大学院フェロー。NHK解説委員、慶應義塾大学環境情報学部教授、放送大学教授などを歴任。専門は英文学と学説史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
153
夏目漱石をかなり深読みしている本です。「坊ちゃん」を政治体制面や風刺的な観点から読み込んでいます。「こころ」を倫理的な側面から分析していて最近の漱石の作品論の中ではかなり異色な感じを受けました。非常に程度の高い本であると感じました。最近漱石の全集が再刊されたりして、ミニ漱石ブームが起きているようですがひとつの成果なのだと感じました。2017/01/12
fseigojp
27
これは大当たりでした 冒頭の『坊ちゃん』の解説は圧巻2016/12/29
マカロニ マカロン
13
個人の感想です:B。『坊っちゃん』の本質は風刺小説であるとして、坊っちゃんが寝泊まりする宿「山城屋」は陸軍省の公金を費消して自殺した山城屋和助、校長の狸は山縣有朋、教頭の赤シャツは桂太郎、野だが西園寺公望を当てこすって『ガリヴァー旅行記』並みの皮肉が込められているとする。また『こころ』は百年にわたる気宇壮大な悲劇、大逆事件を撃つ悲壮な証言と主張。著者は返す刀で森鷗外は大逆事件弾圧に関与し、二重スパイ同然の卑劣漢だと断罪する。果たして漱石がそこまで政治的な問題に関心を持っていたのか、私にはわからない2023/11/15
浅香山三郎
12
赤木さんをジャーナリストとして知つてゐたので、かういふ本も書かれるのかと驚いた。新書といふ形態を配慮したのか、既存の学説が具体的に誰の何の本を指すか分からないのが残念だが、『坊っちゃん』の読み方などの提示は面白い。『文学論』とヘーゲル主義との関はりなどについては、『文学論』を読んだ上でないと当否を判断できないなといふ印象。2018/02/24
ホシ
12
晦渋な文章もあって、感銘を受けるには至らなかったが、もう一度、漱石を再読したくなる一冊だった。「人と人の関わり、道徳と道徳の関わり、それらの集約が社会であり、経済であり、政治であり、ひいては時代精神になり、そのような集団意識が文学の内容だ」(p.36)。漱石文学はこれに尽きるんだろうな。文明の利器である列車に飛び乗ったら、いつの間にか窓外が暗闇だった…現代は『こころ』が書かれた時代と重なるのではないか?そう思わずにはいられない。善を欠いた文明の発展にブレーキを踏むための心を漱石作品に読み、身につけたい。2017/06/15
-
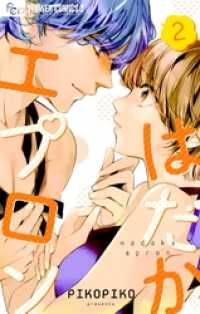
- 電子書籍
- はだかエプロン(2) フラワーコミック…