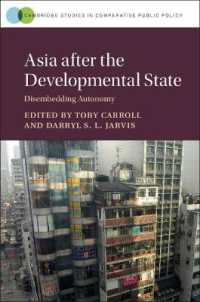出版社内容情報
大名たちの戦勝祈願、庶民たちの篤い信仰、そしてキリスト教。戦国時代の「宗教」の諸相を読み解く。
内容説明
乱世の英雄たちが入り乱れ、激しい戦争を繰り広げていた戦国時代。日々、不安定な世界の中で激動にさらされていた人々は、心の安寧をどこに求めたのか?大名たちの戦勝祈願、庶民たちの本願寺信仰、そして新しく日本に入ってきたキリスト教―当時の信仰の諸相を、「天道」という観念に注目しつつ読み解く。
目次
第1章 合戦と大名の信仰(川中島合戦と宗教;戦争の呪術・大名の信仰)
第2章 一向一揆と「民衆」(加賀一向一揆の実像;石山合戦の実像;共存の信仰世界;本願寺教団と民衆)
第3章 キリスト教との出逢い(宣教の始まり;宣教師のみた日本人の信仰;織田信長とキリシタン)
第4章 キリシタン大名の誕生(大友宗麟の改宗;家中のキリシタン信仰)
第5章 「天道」という思想(「天道」と諸信仰;統一政権の宗教政策;秀吉の伴天連追放令)
著者等紹介
神田千里[カンダチサト]
1949年生まれ。東京大学文学部卒業、同大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。高知大学教授を経て、東洋大学文学部教授、博士(文学)。専攻、日本中世史(中世後期の宗教社会史)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Book & Travel
42
戦国時代の信仰がどのようであったか、戦に臨む大名の信仰、一向一揆やキリスト教布教の実態、そして信仰全体の鍵となる天道について、最近の研究を元に述べられる。信長と本願寺が敵対したのは政治的理由だったこと、秀吉の伴天連追放令は宣教師による寺社の破壊、信仰の強制、子供の人身売買が理由だったことなど、興味深い話が多かった。現代は宗教への関心が薄らいでいるようで、事故現場に花を供えたり、建設工事で安全を祈願したり神仏に頼る習慣は残っている。戦国びとと我々の隔たりは予想外に小さいという後書きに、納得するものがあった。2018/09/27
白隠禅師ファン
18
戦国びとの宗教観念を探る本。戦国時代というとこの時代の人は、武将であれ民衆であれ、鎌倉〜室町までの中世人が持っていた、宗教・呪術性が薄まり、合理的な面を持ちつつあるイメージがつきがちであるが、やはりそれは一面的な見方であると感じた一冊。一向一揆、織田信長の一向宗への対応の再考や戦国びとのもつ「天道」思想が神仏と等値の関係にあったというのはなかなか興味深かった。2025/05/19
takka@ゲーム×読書×映画×音楽
12
戦国時代で宗教といえば、戦勝祈願・一向一揆・本願寺・キリシタン大名などがキーワードとして挙げられると思うが、実際どのように捉えられていたのか考察している本。信長は比叡山焼き討ち、秀吉は伴天連追放令で宗教に弾圧的なイメージを持たれているが実際のところどうだったのか。また、キリシタン大名はなぜキリスト教を信仰することになったのか。歴史の授業では表面的な知識でしか教わってこなかった宗教観を知ることで、新たな側面を知れた本だった。2024/02/17
富士さん
5
著者が前提にしている、合理主義的な思考は宗教と相対するという考え方を共有しないので、本書の論旨は必ずしも同意できるものではありませんでしたが、宗教決定論的歴史観に反対する結論はまさに同感でした。世の中には宗教によって人間を色分けしようとする考えが多く見られますが、宗教の説く教えが人を縛るというよりも、人の生き方が宗教を縛っている側面が大きいように思います。宗教を理由に戦いが起こる場合も、その実、そこに住む人たちが宗教と不可分の自分たちの生き方を守るためにする場合の方が多いのが、現実ではないのでしょうか。2019/03/08
MUNEKAZ
5
戦国大名と宗教の関わりについて。個人的にはキリスト教に関する件が興味深かった。キリスト教に対する批判としてその教えではなく、他宗への攻撃が挙げられているのは、他地域での宣教師の振る舞いを思えば納得だし、その攻撃が大友宗麟らキリシタン大名にも向いていたのは面白い。思うに大名がキリスト教を受容するということは、それを軸とした支配システムを導入するのと同じであり、すでに各権門による体系が出来上がっていた戦国日本では難しかったのではないだろうか。2017/03/05
-

- 電子書籍
- 異世界帰りの元勇者ですが、デスゲームに…
-
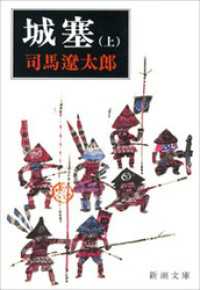
- 電子書籍
- 城塞(上) 新潮文庫