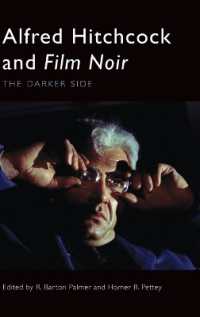内容説明
選挙の仕組みに難点が見えてくるとき、統治の根幹が揺らぎはじめる。選挙制度の欠陥と綻びが露呈する現在の日本。多数決は本当に国民の意思を適切に反映しているのか?本書では社会的選択理論の視点から、人びとの意思をよりよく集約できる選び方について考える。多数決に代わるルールは、果たしてあるのだろうか。
目次
第1章 多数決からの脱却(多数決を見つめ直す;ボルダルール;実用例;是認投票)
第2章 代替案を絞り込む(コンドルセの挑戦;データの統計的処理;さまざまな集約ルール)
第3章 正しい判断は可能か(真実の判定;『社会契約論』における投票;代表民主制)
第4章 可能性の境界へ(中位投票者定理;アローの不可能性定理;実証政治理論;最適な改憲ハードルの計算)
第5章 民主的ルートの強化(立法と執行、主権者と政府;小平市の都道328号線問題;公共財供給メカニズムの設計)
著者等紹介
坂井豊貴[サカイトヨタカ]
1975年広島県生まれ。1998年早稲田大学商学部卒業、2000年神戸大学経済学修士課程修了、2005年ロチェスター大学経済学博士課程修了(Ph.D.)。横浜市立大学経営科学系、横浜国立大学経済学部、慶應義塾大学経済学部の准教授を経て、慶應義塾大学経済学部教授。専攻、社会的選択理論、メカニズム・マーケットデザイン(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 5件/全5件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
108
社会的選択理論の分野を多数決という民主的手段としてはベストチョイスと思われる選択方法で具体的に説明しています。ゲームの理論や意思決定論、行動経済学あるいは契約理論と若干かぶる分野もありますが、最近の新しい経済学分野であると思われます。具体的な例を用いて説明してくれておりわたしは比較的わかりやすく感じました。ただ新書なのである意味説明できる範囲は限られていて若干不満が残りました。2015/10/15
Miyoshi Hirotaka
77
サッカーは勝ち点、オリンピック開催都市は最下位落選。一位を選抜する方式は多様。一方、選挙は一人に満点をつけ、他の候補者を零点にする。これは、革命や内戦のような野蛮な方法に比べれば文明的。しかし、有権者の増加、政治の選択肢の多様化、政治家の質や投票率の低下など民主主義の黎明期に比べれば想定外のことが多い。また、マスコミの偏向、捏造報道、ネットによる暴露により世論が流動化。ポピュリズムが成立し易くなった。ナチスは新聞と演説で独裁を獲得、ラジオの利用は政権後半。民主主義の基盤は約90年前から既に危ういのだ。2019/08/02
けんとまん1007
75
タイトルのとおり、以前は多数決がよいと思っていたが、だんだんと、その思いが薄れてきている。もちろん、否定するものではない。ただ、少数意見に真実があることは否めないという思いが強い。そんな多数決を、いかにして真実に近づけるかということが、随分前から研究されてきているとは知らなかった。今の制度の中でも、いろいろな方式があるのは身近なところからでも知っている。最後のほうの事例は興味深い。評価の仕方を持ち込むということ。奥が深い。2021/02/16
あらたん
64
図書館本。高校生も読んでいるらしいと聞いて手に取った。民意をどう集計するか、それにはルソーの社会契約論以来の長い研究があった。多数決がかなり乱暴な方法であること、多数決以外にも民意を測る方法がたくさんあることを初めて知った。2025/05/03
zero1
64
国会の解散が近いという。【投票のない民主制はない】は確かにそうだ。では民主制とは何だ?日本の公職選挙では、2位には投票できない。もしポイント制で【1位3ポイント、2位2ポイント…】ならばどうか。ナウルやキリバスの例。ボルダやコンドルセの主張は読者が理解しにくい。陪審に直接制と代表制。ロールズにルソーの考え。読メでもよく登場する本屋大賞にも言及。独裁と日本の改憲ハードル。小平市都道の騒動。✴️興味深い内容だが別の切り口で表現できなかったか?疑問もある(後述)。2023/06/12