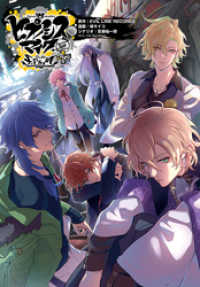出版社内容情報
破格の構図、自由自在なアイデア――歌川国芳(1797~1861)の絵には、浮世絵や時代の枠を超えて伝わってくる楽しさがあふれている。幕末に活躍した国芳は、武者絵・戯画・美人画・役者絵・風景画と、あらゆるジャンルで工夫を凝らした作品を作り続けた。常に新しさを求めた奇想の江戸っ子浮世絵師の代表作70点余を紹介する。
内容説明
破格の構図、自由自在なアイデア―歌川国芳(一七九七~一八六一)の絵には、浮世絵や時代の枠を超えて伝わってくる楽しさがある。幕末に活躍した国芳は、武者絵・戯画・美人画・役者絵・風景画と、あらゆるジャンルで工夫をこらした作品を作り続けた。常に新しさを求めた奇想の江戸っ子浮世絵師の代表作七〇点余を紹介。
目次
第1章 浮世絵の世界へ―初期の画業(浮世絵師になる;デビュー作とヒット作;長い雌伏期)
第2章 人気浮世絵師になる(「通俗水滸伝」シリーズ;拡がる武者絵の世界;斬新な洋風風景画)
第3章 天保の改革を越えて(天保の改革と出版取締り;改革風刺の判じ物;国芳の自負心;時世のトピックを描く;判じ物再び)
第4章 多様な意匠(アイデア自在の戯画;ワイドスクリーン型の大画面;絵で楽しむ実録;見立の楽しさ;真に迫る役者絵)
第5章 晩年の国芳(生人形と錦絵;安政期の作画;国芳の死と後継者たち)
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
203
猫が満載の絵や、為朝が大魚に救われる大判絵など、これまで何枚かは見たことがあったが、こんな風に編年体で体系的に見るのは初めてだ。歌川国芳―まさに破天荒の絵師だ。彼が生まれたのは寛政9(1798)年。世はまさに、動乱の、そして文化的には世紀末的な頽廃と爛熟の色を帯びた幕末だ。例えば、鶴屋南北の『東海道四谷怪談』の江戸・中村座での初演が文政8(1825)年。国芳が27歳の時だ。斬新な国芳の絵だが、彼自身は職人に徹していたらしい。アルチンボルトを思わせる絵、巨魚が跳梁する大胆な構図。浮世絵観に変更を迫る絵だ。2015/04/29
KAZOO
89
歌川国芳は幕末に本で活躍した浮世絵師で私も何枚か見たことはあります。人の顔が人間の体でできていたり、この本の表紙にある「坂田怪童丸」、あるいは宮本武蔵の鯨退治とか結構面白い素材です。この本はその生涯などをたどるとともに作品をカラー写真でたくさん見せてくれます。猫の関連作品も有名ですね。2015/09/06
yumiha
17
国芳が好き♪『ねこと国芳』はすでに購入済で、たまに読み返し(眺め直し?)ているくらい。読み友さんレビューで知った本書によって、これまでの「猫の国芳」だった認識を改めさせられた。天保の改革で絵師に対する弾圧が強められると、その隙間を縫ったような工夫(抵抗?)の判じ絵など。また西洋画からその技法を学び、自分の絵に取り入れたように絶えず表現を広げようとしていたこと。また、妻や娘にはちゃんとした着物を与えても、自分自身は縮緬のどてらに三尺帯の日常だったなど、人間としても愉快だったこと。緻密な研究書だが、楽しい♪2015/06/06
Francis
12
6年間積読して本棚に眠っているのを見つけて慌てて読んだ…というよくあるパターン(^^; 国芳はこの本が出た時ブームになっていたけど、国芳の事は良く知らなかった。改めて読んでみるとすごい画家だったのだなあ、と納得。岩波新書でありながらカラー印刷で作品がたくさん載せてあるのも良い。値段は少し高めだが、この内容であれば文句なし。2020/10/31
himawa
11
新書版なのに絵が綺麗で迫力ある。国芳の魅力を全面に押し出している感じの解説がいい。代表作や判じ絵もたくさんあり。でも解説で触れてるのにその作品が載って無いってとこあったりがちょっと欲求不満になったかなぁ。年玉印から芳桐印になるところに覚悟がみえた。なるほど「ひらひら」の国芳一門の格好良さが納得です。今後も国芳作品ぜひ直に観ていきたいです。2015/02/15