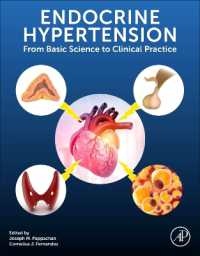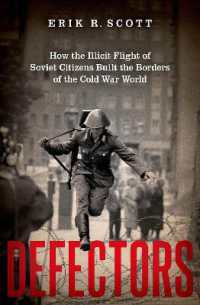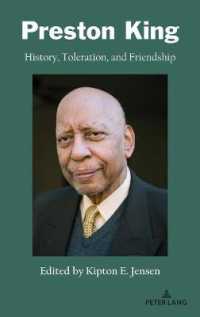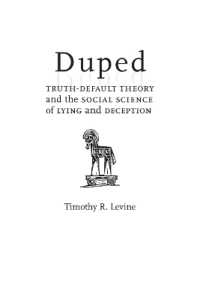内容説明
絵画の基本的な要素は、「形」だが、中国絵画の場合、さらに「気」という要素が加わる。気とは何か?そもそも形とは何か?気と形の関係は?その実例を示しながら、中国絵画独特の気と形について丁寧に説明する。そして、原始から清代まで、代表的な作品一三〇点を紹介し、その魅力を探る。カラー口絵一六頁。
目次
第1章 気の表現の概観
第2章 気と形
第3章 効用第一の時代、あるいは「地下」の時代―漢代まで
第4章 気の時代―六朝時代
第5章 花ひらく多彩な絵画世界―唐代
第6章 山水画の時代―五代から宋代へ
第7章 天才・牧谿の世界―南宋
第8章 元末四大家の登場―元という転換期
第9章 爛熟期の絵画群―明代
第10章 伝統絵画の終焉―清代
著者等紹介
宇佐美文理[ウサミブンリ]
1959年愛知県生まれ。1989年京都大学大学院博士後期課程研究指導認定。信州大学、京都大学人文科学研究所を経て、京都大学文学研究科教授。専攻、中国哲学史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
87
”気”を表現するのが中国絵画では大切なんだそうです。 さすが中国だ。 例えば古代のレリーフで神様の肩の辺りからウニョウニョしたものが出てますが、あれは”気”2020/11/22
sakanarui2
9
著者は美術史ではなく中国哲学史の専門家。中国のそれぞれの時代の画家が、何をどのように描き、それらがどう評価され、後世にどんな影響を与えたのかが解説されている。残念ながら日本美術との関係についての記述はほとんどなし。図版は多いが新書なのでサイズは極小。 でも「気」の描かれ方や、「線で描く」「面で描く」、写実と形態の考え方、作品と作者の人格との関係など、西洋美術を見る時とは異なる視点がとても参加になった。いかんせん人物名と時代がさっぱり覚えられないが、繰り返し実物に触れて流れを理解していこう。2024/09/27
それん君
7
王蒙の絵。「青卞隠居図」。濃淡がはっきりとしている。山の連なりも葉脈や炎みたいに描かれている。僕の好きな絵だなぁ。牛毛皴という技法らしい。今までは水墨画って地味なイメージだった。だから僕の好みは西洋の色とりどりの絵や岡本太郎の絵だった。しかし牛毛皴の絵画を見て新たな発見ができた。2017/03/10
Francis
7
これまでほとんど読んだことがなかった中国絵画の入門書。中国絵画では「気」の表現が重視されていること、文人絵画の方を職業絵画より長い間重視していたことなどこれまで知られていなかったことが良くわかる。日本でも文人画や山水画が描かれているけど、そう言った背景を欠いている日本のものは本場中国のものと異なるみたい。中国絵画についてはまだまだ日本では知られていないことが多いのでこの様な解説書がもっと数多く出ることを望む。2015/07/10
nizimasu
6
著者はこの本の中でメインに解説しているのは、中国の絵画は何を描いているのかということだ。著者はその中で「気と形」という独自の世界観が、中国の絵画には込められている。それは単に形を離れどう見えるのか、そこからどのようなエネルギーなどの流れを表現するのかとう主題の変化を時代を追って解説していて面白い。そのポジションは書画に劣り立体の成立からかなり遅れるなど、目からウロコの話も多いし日本の美術における平面生とも共通するなあと思うばかり。やはり中国の易や儒教的な思想の影響をかなり日本の美術も受けてきた訳で興味深い2014/09/01