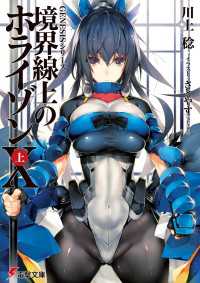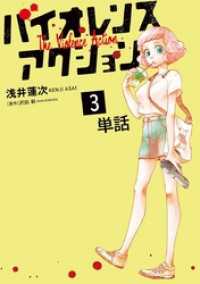出版社内容情報
一九六○~七○年代の女性解放運動のなか、「女のからだ」をめぐる諸問題――性・生理・生殖・妊娠や中絶を、恥や非難を恐れず語り、知識を獲得し、女たちは自らの意識変革を経験した。市場商品と生殖技術の溢れる選択肢という新たな難問に立ちすくむ今こそ、「からだをとりもどした」あの時代を振り返ってみよう。
内容説明
女性解放運動/フェミニズムの諸潮流の中でも、1970年代に全米から展開した「女の健康運動」は、男性医師の管理下にあった性や生殖を女の手に取り戻す、生身の実践だった。日本ではウーマン・リブの優生保護法改定反対運動、さらには生殖技術をめぐる議論へつながっていく。意識変革の時代を振り返り、女のからだの現在と未来を考える。
目次
はじめに―フェミニズムと女のからだ
第1章 女の健康運動―一九七〇年代のアメリカ
第2章 地球を旅する本―『私たちのからだ・私たち自身』の軌跡
第3章 日本のウーマン・リブと女のからだ
第4章 一九八〇年代の攻防と、その後
第5章 生殖技術という難問
おわりに―女のからだは誰のもの
著者等紹介
荻野美穂[オギノミホ]
1945年生まれ。神戸女学院大学文学部卒業、奈良女子大学大学院中退、お茶の水女子大学より博士号取得(人文科学博士)。大阪大学大学院教授を経て、同志社大学教授(歴史学、ジェンダー研究)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
K(日和)
31
フェミニズムについて知りたいと思い読んだ。フェミニズムの文脈で照らされる問題は数多くあるが、それらがどんな文脈で発生してきたのか。もちろん、フェミニズムが生まれなければ差別、抑圧を受けていた人たちがいたからに他ならない。日本で23年生きてきたが、それらを体系的に把握できる環境は十分に整っていない。とりわけ女性の体、健康にまつわる問題がどのように意識され発展し、議論が進んできたか。OBOSとその広まり。生殖することに対する権利、また現代の問題として代理母出産の問題。2018/02/06
みゆき
8
フェミニズムという運動によって現代の女性の権利があるのだと再確認しました。リブに従事した人たちにとって中絶というのは「女のからだ」を男性(医師や政治家ら)から取り戻す手段であり、その運動のなかで絶えず優生思想ではないか、という葛藤が生じていたことも興味深く読みました。そして「女のからだは女のもの」という主張が「からだを切り売りしてもよい」という主張に利用されていってしまう恐ろしさ。そして「本人の希望」という言葉の危うさ。2021/05/27
咲蘭
8
「知識は力なり」フェミニズムの歴史は、F.ベーコンのこの言葉を体現したような出来事の連なりだった。女性が自身の身体についての知識を持たないがゆえに、男性中心主義の社会からいいように扱われてしまう。新しい避妊薬・避妊具の安全性が確認されていないにも拘らず、次々と女性達の子宮に挿入し、最悪死に至ることもあったと知った時は悲しくなった。女性は子供を産む機械でも、実験体でもないのだ。しかし、そのような中で様々な団体が結成され、不都合な状況を変えていった事実には清々しいとさえ感じた。とても勉強になる本だった。2015/01/06
カモメ
7
中絶や避妊、代理出産等、女性の身体に関するフェミニズム運動の歴史が述べられていました。中絶の問題を今まで女性の自己決定という観点から考えた事がなく、興味深かったです。フェミニストの間の対立や、青い芝の会との対立はもっと勉強していきたいと思います。代理出産に関して、女性の自由な権利を肯定する一方で、女性の身体の一部を金銭で代替可能になれば女性さえも資本主義的で商品化されるという批判が興味深く、性産業に関する議論にも通ずる部分があると感じました。2019/09/21
コウ
7
自分の身体(女の身体)のことをどれだけ自分は知っているのだろうか。婦人科に訪ねる機会が増えてから、ようやく“知らなかった”自分に気付く。女という性で生まれたことによる身体との付き合い方、セックス、妊娠、中絶、出産、代理出産、卵子提供、等々…様々な立場(切り口)の主張を通じて改めて考える。まだ経験したこともないことや、一生経験しないかもしれないこともあるが、それでもいざ自分がその立場になれば、また今の自分とは違う自分になるのだろうか。女の身体で生きるということについて、自分自身と向き合うきっかけになった。2019/09/02