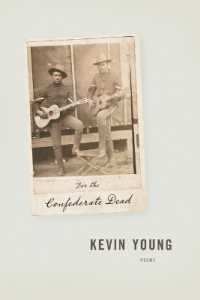出版社内容情報
縄文の集落から弥生の農耕社会へ。稲作の導入を契機とする歴史の大きな分岐点は、しかし、「縄文人から弥生人へ」という単純な交代ではなく、複線としての歴史の始まりでもあった。列島全体を広く視野に黎明期の実像に迫る。
内容説明
「海を越えてやってきた渡来人が、縄文人にかわり、西日本を中心に新しい文化を築いた」という一般的な弥生時代のイメージ。しかし、稲作の導入を契機とする日本列島の歴史の大きな分岐点は、もっと緩やかにして多様なものであった。縄文から弥生への連続性と、地域文化の豊かさに注目しつつ、「複線」としての歴史像を新鮮に描きだす。
目次
はじめに―三つの道筋から日本列島をみる
第1章 発掘された縄文文化
第2章 弥生時代へ―稲作のはじまり
第3章 弥生社会の成長―地域ごとの動き
第4章 弥生文化を取り巻く世界
第5章 生まれいづる「クニ」
おわりに―「弥生時代」を問い直す
著者等紹介
石川日出志[イシカワヒデシ]
1954年新潟県に生まれる。1983年明治大学大学院文学研究科博士課程中退。現在、明治大学文学部教授。専攻は考古学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
85
日本の古代史については、最近どんどん発見が行われたりしてかなりの変更が出てきています。そこのところを取り入れているのと著者独特の考え方が興味を引引き出してくれました。縄文と弥生時代の継続性のようなものを考えておられるようです。「はじめに」のところで著者のそのような基本的な考え方が示されています。2015/10/22
まえぞう
25
岩波新書の日本史シリーズには、古代史、中世史、近世史、近現代史があって、行き掛かりで古代史を読むことになりました。全部読みたくなる性格からは心配ですが、とりあえずこの6冊に取り組みます。著者は邪馬台国機内説ですね。2025/05/24
まえぞう
21
行き掛かり上、こちらのシリーズも2巻まで再読することにしました。ヤマト王権誕生直前までの話しで、邪馬台国も話題になります。最近の通史を扱ったシリーズものでは、邪馬台国畿内説が多いのですかね。特に近年の大和盆地における発掘成果からか、考古学者の著述ではその傾向が強いように感じます。2026/02/14
yamahiko
19
客観的な証拠に立脚し比較検討しながら論を進めていく姿勢に脱帽。読みやすくはないが知らないことも多く刺激的でした。2016/08/13
なつきネコ@着物ネコ
14
縄文時代や、弥生時代の定義というのが、わかったのは収穫だった。縄文時代の当時の日本人が縄文期の自然に適応しながら築きあげた文化。弥生時代は稲作が入り、小規模ながら自然の改変を始めた時代。納得。終わりは古墳の成立となる。さらに、沖縄、北海道では文化系譜が違うのは初めて知った。縄文文化からの連続性の弥生文化その関連は面白い。急な変化や、人種変化で語られる事の多い弥生時代への変化だが、あまりない連続性で語られる。時代の定義がこれほど難しく、線引きが未だに安定しないも難しいな。考古学の難しさを語る一冊だった。2020/11/19