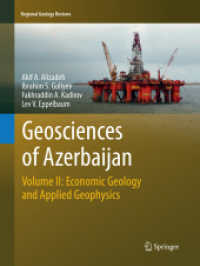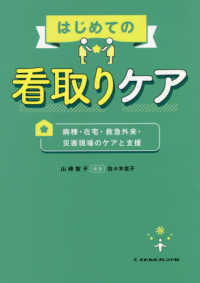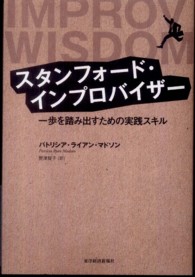出版社内容情報
食品の偽装表示、悪質な訪問販売・・・・・。いま、消費生活の安全をどう確立すべきか。消費者をめぐる法的なしくみをわかりやすく解説。消費者庁など行政、消費者自身に何ができるかを考える。1972年刊行の旧版を全面改訂。
内容説明
食品の偽装表示、悪質な訪問販売、ネット取引でのトラブル…。市場主義やグローバル化が進展するなか、消費生活の安全をどう確立すべきか。消費者の権利を「経済社会の基本的原則」と位置づけ、その仕組みをわかりやすく解説。消費者庁などの行政、あるいは消費者自身に何ができるかを考える。一九七二年に刊行された旧版を全面改訂。
目次
序 脅かされる消費者の権利
第1章 消費者の地位・権利は、いま
第2章 消費生活の安心・安全・自由の権利―市民社会の基本原則と消費者の権利
第3章 商品・サービスを正確に表示させる権利
第4章 市場と消費者―価格決定をめぐって
第5章 情報化社会の中の消費者―情報の提供を受ける権利をどう確立するか
第6章 消費者行政はどうあるべきか
第7章 消費者に何ができるか
著者等紹介
正田彬[ショウダアキラ]
1929‐2009年。1950年慶應義塾大学法学部卒業。慶應義塾大学教授、上智大学教授、主婦会館理事長などを務めた。専攻は経済法(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヤギ郎
13
2010年出版。近年の日本における消費者問題や消費者行政についてまとめている。著者は消費者問題について長年取り組んできた法学研究者。消費者には権利がある。その権利は食の安全を求めることや公正な取引を実現することなど、消費者が健全な生活を送る上で発生するものである。消費者は自らの判断に基づいて消費行動を行ってきた。そこから消費者は企業や問題に対して集団で立ち向かい、また消費者保護を任務とする行政機関(消費者庁)が設立され、消費者問題や消費者行政に変化が現れている。2021/12/28
Humbaba
5
消費者の権利というものは,本来完全に守られていなくてはいけないものである.しかし,残念ながら現在の世界では,正しい情報が必ずしも伝達されているわけではなく,消費者が蔑ろにされてしまうことがある.消費者がしっかりと権利を持ち,それを認識することが重要である.2012/04/27
そ吉
3
消費生活相談員の面接試験対策として読んだが、消費者行政や独禁法等試験の範疇とは違う所が多かった。 ジャンル的には経済法学という分野になるのだそうだが、食品偽装問題など消費者経済史といった感じだった。 1972年初版の旧版を全面改訂した新版であり、消費者庁設立等キャチーな内容もあるがそれでも2010年出版の改訂版には最近のSNS等を使った消費者被害等については触れられていなかった。★★★☆☆2021/12/11
スズツキ
3
旧版が佐高信のオススメらしいので着手。均衡の按配が難しい。2014/06/25
アルゴン
2
★★★★ 消費者があたえられるべき権利について、4つの切り口にうまく分類してまとめられています。最近はモンスターカスタマーなんてのが問題になっていますが、それ以前に確かにこの安全・表示・価格(競争)・情報は消費者が享受できて当然の事項ですね。2013/10/23