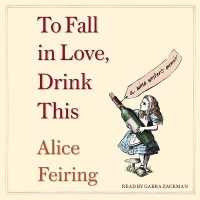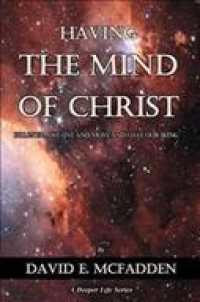内容説明
「賢人」重盛、暗愚な宗盛、「運命の語り部」知盛、こころ弱き人維盛―。それぞれ『平家物語』の描きだしたイメージでよく知られる平家の人びと。しかし「実像」はどうだったのか。当時の貴族社会や合戦の現実に目配りしつつ、人物それぞれの動きを丹念に追うことで、新たな「史実」が浮かびあがる。歴史研究の醍醐味を味わえる一書。
目次
序章 清盛の夢―福原の新王朝
第1章 「賢人」と「光源氏」―小松家の「嫡子」
第2章 「牡丹の花」の武将―はなやぐ一門主流
第3章 内乱の中の二人―平家の大将軍として
第4章 平家都落ち―追われる一門
第5章 一の谷から壇ノ浦へ―平家一門の終焉
終章 さまざまな運命
著者等紹介
高橋昌明[タカハシマサアキ]
1945年高知県に生まれる。1969年同志社大学大学院文学研究科修士課程修了。滋賀大学教育学部教授、神戸大学大学院人文学研究科教授を経て、神戸大学名誉教授。専攻は日本中世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
41
平家といえば今ドラマ化されている清盛だがこの本ではあえて宗盛や維盛辺りにも焦点を当てて書かれたもの。中々逃げ帰ったという一言で史実は済まされずいろんな人の思惑が入り混じるものだなと思った。2012/05/04
鯖
23
物語と歴史の境目が話題になってることもあり再読。平家物語と史実を行き来する本。後書きで歴史学者である御自身のこの著作について「木曾義仲みたいな乱暴で不躾な侵入」って書かれてて、地の文に車で乗り付けてくる司馬遼太郎や昨今のあれこれに比べたら、物語も歴史も双方リスペクトされてて礼儀正しかったですょとなる。これは史実、これは平家物語の記述ってもう少し強調したほうが分かりやすいかも。でも物語で描かれ、受け継がれた彼らの姿も歴史そのものだと思うんだよなあ。勝ち負けじゃないんだから、両方楽しめばいいと思うんだけど。2018/11/19
1.3manen
19
『平家物語』は文学作品。フィクショナルな歴史像(20頁)。政治家の権力の核心は、人事権(73頁)。御家人はもともと家人と呼ばれる主人に仕えた従者(98頁)。義仲らが都に迫ると、多田行綱が摂津・河内をほしいままにうろつき、河尻の船をみな差し押さえ、九州から運上の食糧米を押し取る動きを見せた(132頁)。法皇は義仲・行家両将を蓮華王院御所に召し、平家追討を命じた(150頁)。10月義仲は備中に入ったが、備前・備中の国人らの反抗にあり、退却(158頁~)。2015/09/02
なつきネコ@着物ネコ
18
アニメ平家物語を見て平家を読み返したくなった。武将として活躍したのは知盛よりも重衡。小松家の嫡流は清経。六波羅幕府のような権威を持つのが平家だったという指摘。この一冊から、史実から物語になり庶民が文字化した初めての例が平家物語だった事に気づいた。史実の人と、物語の役割、人々の思いが混ざり昇華した物語。重衡の武功ではなく平家の罪と痛みの象徴へ、平家の勇を表す知盛、過去の優美の象徴として維盛、哀れの平家としての敦盛。苦悩の母としての徳子。物語の全ての仮託を纏めたものが当時の人が見た平家だったのかもしれない。2022/05/02
Toska
14
『物語』でなじみ深い平家の人々のキャラクターに真正面から挑み、史料を通じてその実像を探る。兄・知盛のイメージに統合された勇将・重衡、美少年ぶりは確かな記録でも確認できる維盛、後白河院との関係を軸に最後まであがいた資盛、「狐の狡知と獅子のたけだけしさを兼ね備えた政治家」時忠…あまりにも魅力的な。一方、著者は「史実」の高みから虚構の世界を見下すことなく、『物語』の磨き抜かれた人物造形にも賛辞を惜しんでいない。2024/11/22