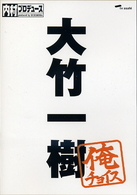内容説明
読者を謎解きに導く巧みなプロット。犯罪にいたる人間心理への緻密な洞察。一九世紀前半ごろ誕生した探偵小説は、文学に共通する「人間を描く」というテーマに鋭く迫る試みでもある。ディケンズ、コリンズ、ドイル、チェスタトン、クリスティーなどの、代表的な英国ミステリー作品を取り上げ、探偵小説の系譜、作品の魅力などを読み解く。
目次
序章 探偵小説の誕生
第1章 心の闇を探る―チャールズ・ディケンズ
第2章 被害者はこうしてつくられる―ウィルキー・コリンズ
第3章 世界一有名な探偵の登場―アーサー・コナン・ドイル
第4章 トリックと人間性―G.K.チェスタトン
第5章 暴かれるのは誰か―アガサ・クリスティー
終章 英国ミステリーのその後―「人間学」の系譜
著者等紹介
廣野由美子[ヒロノユミコ]
1958年大阪府に生まれる。現在、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。専攻は英文学、イギリス小説。著書に『十九世紀イギリス小説の技法』(福原賞受賞/英宝社、1996年)ほか(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
221
探偵は退屈しのぎに謎を解くからこそ人間性の暗部を探求し得る…蓋し名言だ。本書は文学の普遍的要素である人間性の探求が、英国探偵小説にどう受け継がれてきたかを論じている。犯罪者の心の闇に目を向けたディケンズ。孤立無援の被害者を描くコリンズ。ホームズ以降の名探偵たちもそれぞれの流儀で人間性を探ったのだと著者はいう。ただ思うに、人間性への関心もさる事ながら、謎解きという脇道に耽溺する所にミステリのもう一つの愉しみがありはしないか。ロジックやトリックに惹かれる(余り文学的でない)心理にも、もう少し触れてほしかった。2022/05/19
KAZOO
94
この新書は英国ミステリー好きの人にはたまらない本だという気がします。著者は大学でも「ミステリー研究」という講義をしていたようでその延長線上の作品であると思いました。ディケンズ、コリンズ、コナン・ドイル、チェスタトン、アガサ・クリスティーを取り上げその作品についての解説がすばらしい感じです。私はここに上げられている作家がすべて好きなのでこの本も何度か読み直すことになりそうです。2015/08/25
k5
56
古典ミステリフェア②。いきなり副読本ですが。英国ミステリの特徴として「人間を描く」ことにスポットを当てるというのは、ちょっとスベり易いんじゃないか、と失礼なことを思ってしまいましたが、充実した内容の一冊でした。たしかに、ホームズ、ポアロを筆頭にイギリス小説の面白さってキャラクターの面白さだよなあ、と思う時、少しナイーブなくらいの視点設定があっていたのかも知れません。さあ、ガンガンミステリ読むぞ。2025/08/08
ころこ
38
「探偵小説とは、人間の弱点や人間性の暗部を探求するうえで格好のジャンルのひとつだと言えるのである」という文学的な議論の意義があります。本書ではタイトルに「ミステリー」と「探偵小説」のふたつの言葉が用いられています。「ミステリー」を要素として、「探偵小説」をジャンルとして使い分けていますが、「探偵小説」の「偵」の字の当用漢字制限のために「推理小説」になり、「探偵小説」に戻らずにいつの間にか「ミステリー」とジャンル名を変えていたように、あえて「推理小説」というジャンル名を一切使っていないところに文学史を意識し2020/08/13
マーム
27
「探偵小説とは人間を描くものであり、とりわけ人間性の暗部を描き出すうえで、特殊な方法論を有するジャンルである」というのが本書の根幹です。 そして、英国ミステリーの「人間性の研究」という特性がディケンズを祖とし、ドイル、クリスティー等々へと綿綿と受け継がれている、と。「人間が描けているかどうかということが、一般の小説と同様、探偵小説においても作品の成否を決定する重要な基準のひとつとなる」という行を読むと、新本格ムーブメントが起こった頃「人間が描けていない」という批判にさらされたことを思い出しました。(笑)2012/01/28
-
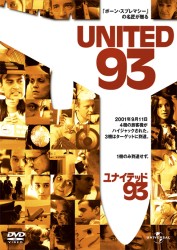
- DVD
- ユナイテッド93