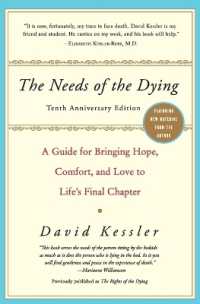出版社内容情報
北海道苫小牧市の郊外に広がる、かつては荒れ果てていた森林。そこで1970年代以降、自然の再生力を尊重する森づくりが進んだ。草花、小鳥、昆虫、そして小川のせせらぎ・・・・・・。市民の憩いの場として、また森林研究の場としても知られる豊かな自然空間は、どのようにして生まれたのか。「都市林」のあり方を示唆する貴重な記録。
内容説明
北海道苫小牧市の郊外に広がる、かつては荒れ果てていた森林。そこで一九七〇年代以降、自然の再生力を尊重する森づくりが進んだ。草花、小鳥、昆虫、そして小川のせせらぎ…。市民の憩いの場として、また森林研究の場としても知られる豊かな自然空間は、どのようにして生まれたのか。「都市林」のあり方を示唆する貴重な体験記。
目次
第1章 森との出会い
第2章 森づくりへの助走
第3章 ヨーロッパの都市林
第4章 共生の森づくりへ
第5章 甦る川、賑わう水辺
第6章 市民の森へ
第7章 フィールド・サイエンスの展開
第8章 森と人の歴史―共生圏の系譜
著者等紹介
石城謙吉[イシガキケンキチ]
1934年長野県諏訪市に生まれる。1961年北海道大学農学部卒業。1969年北海道大学大学院博士課程修了。専攻は動物生態学。現在、北海道大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
46
苫小牧には、ウトナイ湖と並びバードウォッチャーの訪れる定番の場所として北海道大学苫小牧研究林がある。本書は23年間に渡りその林長として2700haの森林を"作り替えた"動物生態学者の記録。意外なのは、この森はドイツ由来の近代林学のもとで木材生産のための人工林(エゾマツ)に植え替えられていたこと。しかしそれに失敗して荒れ果てた森林になっていた。これを生まれ変わらせたのだ。面白いのは原始林に還すのではなく、市民が親しめる森林として、川を再生し池を堀り林道を走らせ鳥を餌付けし、人工の自然を"創っ"たことだ。↓ 2015/04/14
mitei
43
北海道のある森林を復活させる過程を書いた一冊。タイトルの通り物語がついていることもありあまり学術的なことはなく、著者の体験談といった印象が強い。2012/08/24
テディ
9
志と行動の大事さを学びました。この夏休みは自然公園を散歩します。ガチの森林にも行ってみたいですけどね。2017/07/28
gotomegu
6
棚ル庫。荒廃した北大演習林をドイツ型の施業で森を復活させただけでなく、都市近郊林として整えていった話。経済林としても成り立たせ、なおかつ近隣に住むひとたちにも親しまれる森づくりを目指したところがすばらしい。苫小牧北大演習林は、今でも鳥や動物の観察、研究に使われ、市民にも愛されている。かつて日本は森林と共生してきた。明治以降効率的に木材を育てる場として位置付けられ、針葉樹が植林され続けた。50年前から取り組まれてきた都市近郊林が、なぜ他の地域に広がっていかなかったのか、そこを知りたいと思った。2025/11/17
1.3manen
2
中山間地域では森林の荒廃が問題となっている。手を入れるマンパワーの問題、資金の問題などあろうが、治山や造林の意義を感じざるを得ない。獣害や病虫害があるのは、手入れを怠ってきたゆえん。大きなことは評者も言える立場にないが、鋸や斧を持って間伐作業ぐらいはやってみたい。森林セラピーという癒しにも活用される森林。森林が文化として市民も育てる主体になることが大切なことであると思った。2012/06/20
-

- 電子書籍
- アオのハコ 17 ジャンプコミックスD…
-

- 電子書籍
- スキル【再生】と【破壊】から始まる最強…