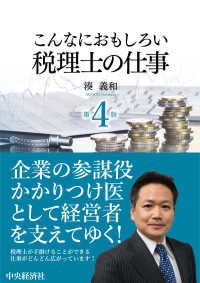内容説明
アメリカ発金融危機の影響が瞬く間に世界に広がり、地道に働く庶民にとって、将来不安は募るばかり。そんななか、金融トラブルに巻き込まれる人があとを絶たない。被害に遭わないために、まずどんな知識が必要か。そもそも普通の人々にとって「投資」とは何なのか。原点に立ち返り、「リスク」を見据えることから考察する。
目次
第1章 世界の金融危機、身近な金融リスク(世界金融危機;身近に存在する金融被害 ほか)
第2章 金融リテラシーの時代(金融トラブルに巻き込まれないために;米国の金融教育 ほか)
第3章 金融知識を身につける(債券の基礎;格付けの落とし穴 ほか)
第4章 金融商品を見分ける(債券投資―危険な高利回り債;仕組み預金 ほか)
第5章 社会人のための金融教育(体系的な金融教育の必要性;大学生の金融知識 ほか)
著者等紹介
新保恵志[シンボケイシ]
1955年石川県生まれ。1978年一橋大学経済学部卒業。同年4月、日本開発銀行(現日本政策投資銀行)入行。1988年住友信託銀行入社、調査部にて、社債、転換社債、ワラント債などの証券分析、オプション、スワップ、先物などのデリバティブ関連の分析を行う。2002年より東海大学教養学部教授。専攻は金融論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
coolflat
15
岸田政権は「貯蓄から投資へ」とかしょうもないことを言い出したが、国が庶民に向かって投資を煽ることがいかに危険かよくわかる。投資や金融商品にはリスクが存在し、所得倍増することもあれば所得半減もある。国が老人の貯蓄をターゲットにしているのはまるわかりで、国が煽れば当然、金融・投資詐欺が湧いて出てくるのだが、その時社会問題化したらどうするのか。自己責任か?金融リテラシーは一朝一夕に身につかない。国は投資をすれば所得が倍増になるという詐術をする前に、少なくとも国民に(本書が主張する)金融・投資教育をせねばならない2022/06/22
壱萬参仟縁
8
金融危機に見舞われたが、今のアベノミクスもその金融資本主義にどっぷりと浸からないと他に手段がない、かのような錯覚を与えられる。実体経済、地域経済や家計のすそ野の広さを忘れてはならないと思う。ワラントとは、株式購入権で、株価上昇率以上に価格が上がるというのを売り物に、売りつけるものであるようだ(26頁)。一長一短、一長のみを見ていては足元をすくわれる。しかも、使用期限があるようだ。他にスワップなどの概念、用語も説明されていく。最近では1万円から投資家に、のようなのもCMでみる。U.ベックのリスク社会も想起。2013/08/06
chayka2
2
あの銀行で必ず紹介される謎の金融商品は「変額個人年金保険」なのだと分かった。その存在意義は本書を読んでもよく分からないですが…著者も投資信託と直接契約したほうがマシだと言い切っている。オプションをつけて見かけの金利を高くする方法なんかは、よう考えるな…と感心?してしまった。手数料を意識せよ、というのは今後(当然オプション無しの)社債を証券会社から購入する場合にも当てはまることだな、と。2024/09/15
〆さば
2
良書。予期しない金融トラブルに巻き込まれないための金融知識を学ぶことができる。金融商品と付き合う上で気を付けるべきリスクや、日本では軽視されがちな手数料の重要性などについて書かれている。また、オプションや投資信託、変額個人年金保険など個々の金融商品についてもわかりやすく解説されているため、「名前を聞いたことはあるが、具体的なことはわからない」という人でも読みやすい。2012/08/19
むとうさん
1
株式や債券投資に関する本は星の数ほどあるが、「リスク」に焦点を当てた本は珍しい。投資の基本は常に「ハイリスクハイリターン」か「ローリスクローリターン」であり、高利回りの裏には見えないリスクが存在する。ある意味では当たり前なのだが、メカニズムとして一通りをわかりやすく説明しているので、資産運用を考える人は読んで損はない。ただ、ちょっと銀行や証券会社を悪者扱いしすぎではないか?金融の社会的意義を最後に強調するなら、金融機関の意義も強調すべきだろう。2011/03/21