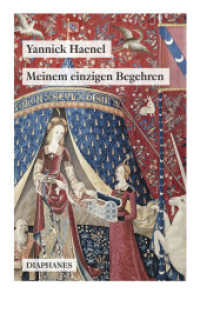内容説明
英語、韓国語、中国語など外国語を学ぶ人は多く、また日本語教育に携わる人も増えている。だが各種のメソッドや「コツ」は、果たして有効なのだろうか。言語学、心理学、認知科学などの成果を使って「外国語を身につける」という現象を解明し、ひいては効率的な外国語学習の方法を導き出す、「第二言語習得(SLA)」研究の現在を紹介する。
目次
第1章 母語を基礎に外国語は習得される
第2章 なぜ子どもはことばが習得できるのか―「臨界期仮説」を考える
第3章 どんな学習者が外国語学習に成功するか―個人差と動機づけの問題
第4章 外国語学習のメカニズム―言語はルールでは割り切れない
第5章 外国語を身につけるために―第二言語習得論の成果をどう生かすか
第6章 効果的な外国語学習法
著者等紹介
白井恭弘[シライヤスヒロ]
東京生まれ。上智大学外国語学部英語学科卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)修士課程(英語教授法専攻)。博士課程(応用言語学専攻)修了、Ph.D.(応用言語学)。大東文化大学外国語学部英語学科助教授、コーネル大学現代語学科助教授、同アジア研究学科准教授などを経て、ピッツバーグ大学言語学科教授。言語科学会(JSLS)会長。専攻は言語学、言語習得論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
314
外国語を学ぶ前に読んでおきたい1冊。中々歳をとると外国語が入らなくなるなぁと実感。子どもの間から学びたいと言うがやはり母語の重要性もあると思った。2017/11/16
kaizen@名古屋de朝活読書会
138
岩波新書愛好会】第二言語習得論ではないかも。外国語研究論。「発音は完璧でなくても構わないが、通じれば日本語なまりでもよい」は、国際人の常識。 中国人が中国語英語を話し、スペイン人がスペイン語英語を話しているときに、 日本人だけが、日本語英語を話してはいけないのでしょうか? スペイン語は母音が日本語とおなじようにだいたい5つのためか、日本語英語は分かりやすいといわれます。国際的に通用するのは、日本語英語だと感じています。第二言語習得は、言葉のプロになるためでなく2013/06/27
KAZOO
122
英語に限らず外国語学習に係る一般的な習得方法などが書かれています。母国語でない第二言語習得論ということで言語学的な観点からのアプローチによるものです。とくに第4章の「外国語学習のメカニズム」と第5章の「外国語を身につけるために」、第6章の「効果的な外国語学習法」が参考になりました。2016/01/06
ntahima
45
日本語教育能力検定試験の準備をしていた頃、この手の本をたくさん読んだことを懐かしく思いだした。当時読んだ本と比べて非常に読み易くコンパクトに纏まっている。内容はオーソドックスで当然のことながら奇跡の速習法は出て来ない。第二言語習得理論についてまんべんなく触れているがインプット重視の立場のように思える。先日、読了した『英語学習7つの誤解』では外国語を話すのが自然な環境に身を置く重要性(これは外国に住むこととはイコールではない。)を学び。本書ではインプットの重要性を再認した。語学教師を目指している方にお勧め。2012/12/22
那由田 忠
21
インプットとアウトプットとどちらが大事か、という議論があって、文法などしっかりとしたインプットがあった上で適宜アウトプットが必要だという、ある種常識的な結論に落ち着きそうだ。いまの日本はちょっとアウトプットに偏ろうとしているかもしれない。今までがアウトプットを無視しすぎた反動なんだろうけど。2018/09/30
-

- 電子書籍
- 姫の夫は毎晩変わる 【単話版】: 7 …
-

- 電子書籍
- 水に流せない「水」の話 常識がひっくり…