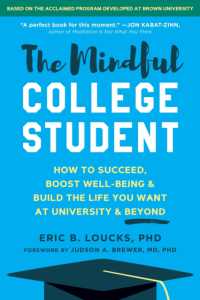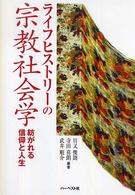出版社内容情報
古典語の研究からタミル語との遭遇へ──。
日本語は、いつ頃どのように生まれたのか。南インドのタミル文明の到来の中に、言語の形成を位置づける。
内容説明
日本語は、いつ頃どのように生まれたのか。「日本精神」の叫ばれた戦時下、「日本とは何か」の問いを抱いた著者は、古典語との格闘から日本語の源流へと探究を重ねた。その途上で出会ったタミル語と日本語との語彙・文法などの類似を語り、南インドから水田稲作・鉄・機織などの文明が到来した時代に言語も形成された、と主張する。
目次
1 タミル語と出会うまで(日本とは何か;国語学を手段として;古典語の研究)
2 言語を比較する(言語の比較ということ;タミル語との遭遇;単語の対応(1)母音と子音と
単語の対応(2)文例とともに
文法の共通
五七五七七の韻律)
3 文明の伝来(水田稲作は南インドから;鉄も南インドから;機織も南インドから;結婚の方式;小正月の行事;神という存在;石の墓、土の墓;グラフィティ(記号文))
4 言語は文明に随いて行く(船と海上交通;何を求めて日本に来たか;朝鮮語にもタミル語が来ている;タミル語到来以前の日本語;日本語の歩んだ道)
著者等紹介
大野晋[オオノススム]
1919年東京に生まれる。1943年東京大学文学部卒業。専攻、国語学。学習院大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
62
日本の弥生時代はタミールより、てどうしてこうなったんだろう。 日本語とタミール語、似てるように思えない。 そっくりな壺とかはあるけど、輸入されたのかもしれないし、船乗ってきた人もいたかもしれない。 五七七という歌のリズムも一緒ですって。 日本語タミール起源説は無理あるように思うけど(中韓を出し抜いた満足感があるのか)2022/05/18
ふくとみん
17
大野晋最後の本と思います。母音終わりのポリネシア語のひとつが使われていた日本にタミル語が到来してヤマトコトバが作られたとする説明。本を読む間はなるほどと思うけどそこまで海上交通が可能であったのか不思議な気にもなる。若い頃読んだ懐かしさで読みました。2024/09/17
takeapple
7
日本語タミル語起源説についてのわかりやすい解説本。批判されればされるほど、著者の学説は自身の中で強固になっていくんだろうなあ。とっても面白い。2012/04/01
kaizen@名古屋de朝活読書会
5
日本は極東で大陸の端。 多くの文化を受け入れ。 4大文明のインド文明と中国文明のよいところを入れてる。 仏教と儒教は日本文化の基礎の二つ。 言語の面では漢字が中国の文明の資産。インド文明の遺産も不思議でない。 本書は当然のことを一つの筋書きで書き下した物。朝鮮半島の言語と日本語との間の関係の分析は、隣接している国であるため、重要。 一番近くの言語との関係と、それ以外の言語との関係を、体系的に説明してもらえるとありがたい。 アイヌ語との関係が分かると嬉しい。http://bit.ly/10CJ7MZ2008/06/30
ひろゆき
4
日本語と南インドのタミル語との共通点を分析し、圧倒的な文化の力の前に日本語が侵食され、タミル語が日本語の源流の一つとなったことを主張。水田稲作、食糧、祭などを中心に共通の語彙の紹介から始まり、果ては言語を離れ、考古学の分野にも踏みいる。著者の熱意がホント感じられる。中国朝鮮経由でなくインドと直接関係してたのねえと納得するとともに、古代史のスケールに圧倒された。2013/07/01