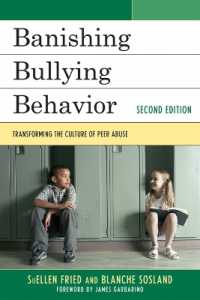出版社内容情報
日本経済の「後進性」が問題にされ、近代化・合理化が必要だと熱心に叫ばれていた時代から、「経済大国」としての役割を期待されるようになる時代まで。「成長神話」はいかにして浸透し、「ゆがみ」を生じさせていったのか。
内容説明
日本経済の「後進性」が問題にされ、近代化・合理化の必要性が熱心に叫ばれた時代から、「経済大国」としての地位を確立する時代まで。「経済成長への神話」はどのように浸透し、また「ゆがみ」を生じさせていったのか。人々の欲求と政治の思惑はいかに寄り添い、あるいはすれ違い続けたのか。通説に大胆に切り込む意欲作。
目次
第1章 一九五五年と一九六〇年―政治の季節(転機としての一九五五年;独立後の政治不安;保守合同と五五年体制;国際社会への復帰;春闘と三池争議;日米安全保障条約改定問題;五五年体制と戦後民主主義)
第2章 投資競争と技術革新―経済の季節(経済自立から所得倍増へ;投資とその制約要因;「技術革新」と新産業育成;「見せびらかしの消費」の時代)
第3章 開放経済体制への移行―経済大国日本(ベトナム戦争下のアジア;開放体制への移行;証券恐慌と大型合併;大型合併と企業システム;「成長志向」への異議申し立て)
第4章 狂乱物価と金権政治―成長の終焉(二つのニクソン・ショック;沖縄返還;列島改造と狂乱物価;二つの石油危機;企業の社会的責任と金権政治)
著者等紹介
武田晴人[タケダハルヒト]
1949年生まれ。東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。現在、東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授。専攻は経済史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
coolflat
fseigojp
purupuru555
Akiro OUED
瓜月(武部伸一)
-
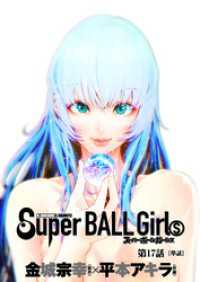
- 電子書籍
- スーパーボールガールズ【単話】(17)…
-

- 和書
- 新臨床栄養学 (増補版)