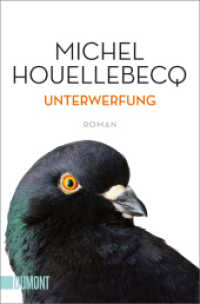内容説明
マレー半島上陸と真珠湾攻撃によって開始された「アジア・太平洋戦争」。なぜ開戦を回避できず、長期化したのか。兵士や銃後の人々、アジアの民衆は、総力戦をいかに生き、死んでいったのか。矛盾を抱えて強行され、日本とアジアに深い傷跡を残した総力戦の諸相を描きながら、日米交渉から無条件降伏までの五年間をたどる。
目次
第1章 開戦への道(三国同盟から対米英開戦へ;戦争の性格;なぜ開戦を回避できなかったのか)
第2章 初期作戦の成功と東条内閣(日本軍の軍事的傷利;「東条独裁」の成立)
第3章 戦局の転換(連合軍による反攻の開始;兵力動員をめぐる諸矛盾;「大東亜共栄圏」の現実;国民生活の実状)
第4章 総力戦の遂行と日本社会(マリアナ諸島の失陥と東条内閣;戦時下の社会変容)
第5章 敗戦(戦場と兵士;本土空襲の本格化と国民;戦争の終結へ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぴー
73
東条内閣成立〜アジア・太平洋戦争の敗戦までの時期を扱った通史。主に、太平洋戦線がどう展開されたのかについて書かれている。戦局悪化とともに、日本社会も変化した点を指摘している。特に、女性の立場や伝統的な家族の在り方を変化させたことが、自分にとって新しい発見になった。日米の兵器等の比較資料を見ると、昭和18年初期の段階で厳しいことが明確。以降の日本側は苦戦が多く、悲惨な状況下であったことが述べられており、終戦までを読むと気が重くなる。戦争責任の曖昧化や戦争体験者が減る中で色々と考えさせられる一冊でした。2025/05/04
nnpusnsn1945
54
太平洋戦争についての概要をおさらいできる。戦場や市民、植民地もうまくカバーできている。パラパラと読むだけでも頭に入りやすい。なお、本書では満洲、中国戦線も包括するため「アジア・太平洋戦争」と呼んでいる。2021/03/06
おたま
39
1941年から始まったいわゆる「太平洋戦争」の期間を対象としている。しかし、満州、中国、ソ連、東南アジアのこと等も取り上げているために、「アジア・太平洋戦争」と規定されている。この本では、特に戦争の中での人々の具体的な生活、戦場での兵士の在り方などを、想像力を駆使して再構成すること。さらに戦争責任の問題も明確にすることを目的に収めている。通史と言っても、戦史のみに終わらなず、戦争をその全体において捉えようとしている。通史としても、アジア・太平洋戦争の実像の把握としても、優れていると思う。2021/03/27
ケー
29
近現代史には割と昔から興味はあったけれど、その殆どが民衆史、民俗学的なアプローチばかりで政治史、戦争史としては教科書的な知識しかなかった。そんな自分でも丁寧に学べる好著。本書は一冊で日本にとって大きな転換点となったアジア・太平洋戦争について解説。人名はもちろん多いがそれ以外の専門用語は比較的少ないので読む上でのハードルは低め。読む前に高校日本史くらいの知識があればなお良し。最初の一冊としては充分。2017/10/09
Toska
27
戦争史としてはコンパクトでオーソドックスな構成だが、非常に緻密。例えば軍事行動を予算面で支えた「臨時軍事費」など、重要でありながら従来あまり注目されてこなかったトピックに焦点が当てられている。戦争を通じた産業構造の変化、小作人や女性の相対的な地位向上と社会の平準化、「旧い公的タテマエ」への幻滅による「民衆のエゴイズム」の増幅など、戦後日本を準備する下地がすでに形作られていたという指摘も重要。2023/07/05