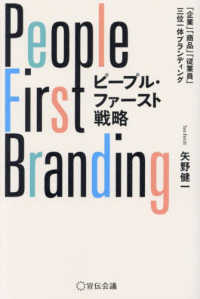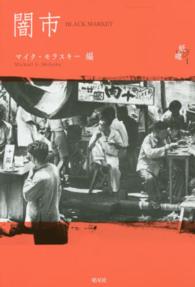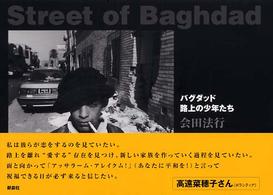出版社内容情報
現代に「参加」して生きるとはどういうことか?
サルトル生誕百年。世界的に血なまぐさい暴力が繰り返される今こそ、「人間とは何か」を問い続けた二十世紀最大の知識人の思想が、新たなリアリティとともによみがえる。
【目次】
まえがき
I 『嘔吐』から─出発点
1 私にとっての『嘔吐』
2 <人間>の思想の萌芽
サルトルの肖像─1
II 戦争、収容所、占領─戦時下の思想形成
1 <奇妙な戦争>と戦中日記
2 『存在と無』を読む
3 <アンガジュマン>思想の形成
サルトルの肖像─2
III 自由の実現は可能か─戦後の展開を読む
1 実存主義宣言
2 自由と連帯─小説『自由への道』と戯曲群
3 『聖ジュネ』または非人間の復権
4 家族論として読む『家の馬鹿息子』
サルトルの肖像─3
IV 闘うサルトル─知識人としての〈参加〉
1 マルクス主義との格闘─『方法の問題』から『弁証法的理性批判』まで
2 「サルトルを銃殺せよ」─アルジェリア戦争
3 五月革命と毛派
4 葬儀の日
サルトルの肖像─4
V サルトル再審─二十一世紀へ
1 <父親殺し>の後に
2 破壊者/建設者、サルトル
3 友愛と暴力、そして倫理
4 人間化の運動─二十一世紀のサルトル
あとがき/参考文献/略年譜
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nbhd
19
サルトルは色々ややこしいことを考えていて、この本も簡単じゃない。だけどそのぶん、サルトルその人に興味が湧いてきた。サルトルの身長は150cmくらい、指は短く小さな手をしていて、斜視、それから誰もが気にする変な声をしていたらしい。さらに蟹とか甲殻類を死ぬほど嫌っていたという。これだけで、もうたっぷり興味深いのだけど、ボクシングに熱を入れたり、喧嘩っぱやくて同僚をぶん殴ったりの暴力沙汰も起こしていたらしい。これからちょっとずつサルトルを読んでみようと思っているのだが、サルトル基礎データは十分インプットできた感2014/10/31
浪
14
サルトルや実存主義が流行っていた頃の雰囲気を感じることのできる解説書。中でも「嘔吐」の解釈は興味深いものがある。「人は生まれながらにして自由の刑に処されている」のが実存主義の考えである。だが、先行世代によって豊かな生活環境が確保された状態で生まれ育ったことにより、今の日本の若者には主体性や自由が与えられていない。すでに欲しいものが揃っているから頑張る必要がないのだ。斜陽国日本という揶揄がさらに希望を奪い、安定志向へと誘導する。そして僕はそんな状況に苛立っている。2018/12/28
swshght
12
サルトルの思想は難解だ。すでに二度も挫折している。そこで入門書を読むことにした。ベルクソンやバタイユなどのフランス現代思想に触れるときも、このアプローチが大いに役に立った。著者は「読者」としての視点を基盤としている。研究者としてサルトル思想の真理や核心に迫るというよりは、あくまでも自身の読書体験を媒介として彼の全体像を浮かび上がらせる。そのため、「眼から鱗が落ちた」といった感想や体験談がやや散見される。また、サルトルの思考の形成や転換を伝記的に記述しているという点で、これは評伝として読むことも可能だろう。2013/02/06
む
9
高校一年生の時にあることがきっかけで海外古典文学にどっぷり使っていた時に、わたしはサルトル水入らずを読み、サルトルの存在を知った。この本では「嘔吐」や「存在と無」などサルトルの作品を取り扱いサルトルの思想や政治活動または人生を読み解いていく。《実存主義》というサルトルの代表的なものの存在は知っていたが、この本を読んでそれについての理解が深まったように思う。はじめは読むのに苦戦したが20ページを過ぎるあたりからスラスラと頭に入ってきて、大体1時間程度で読み終われる、(コメントへ)2015/01/13
プータン
8
サルトルについて、著者のフィルターを通してまとめた入門書。サルトルについて無知な私には、著者の思い入れが伝わってくるこの本はかえって読みやすかった。「サルトルは人間主義」という筆者の主張は大筋間違っていないように思うが、このあたりはサルトル本人の著作を読んで検討して行きたい。2013/03/31