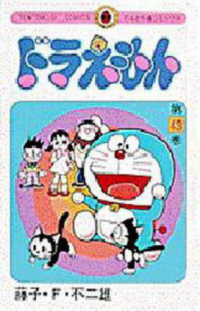内容説明
一九九〇年代、日本の音楽産業は急激な成長を遂げる。CDのミリオンセラーが続出し、デジタル化や多メディア化とともに市場規模は拡大し続け、いまや日本は世界第二位の音楽消費大国である。こうした変化をもたらした「Jポップ」現象とは何か。産業構造や受容環境の変化など、音楽を取り巻く様々な要素から鋭く分析する。
目次
第1章 「J」の時代のポピュラー音楽
第2章 デジタル化は何をもたらしたか
第3章 テレビとヒット曲
第4章 「ココロ」の時代の音楽受容
第5章 日本という音楽市場のかたち
第6章 Jポップ産業の挫折―急成長の十年が終わって
著者等紹介
烏賀陽弘道[ウガヤヒロミチ]
ジャーナリスト、1963年京都市生まれ。86年に京都大学経済学部を卒業し、朝日新聞社記者になる。91年から2001年まで『アエラ』編集部記者。92年にコロンビア大学修士課程に自費留学し、国際安全保障論(核戦略)で修士課程を修了。同誌では音楽・映画などポピュラー文化のほか医療、オウム真理教、アメリカ大統領選挙などを取材。98年から99年までニューヨークに駐在。03年に退社しフリーランスに
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ゲオルギオ・ハーン
24
2005年発行。「Jポップ」とは不思議なジャンルである。日本の有名な音楽というくらいで文化の流れの中で確立されたものではない。本書はJポップというジャンルの誕生と発展を時系列で追っていくことにより、日本におけるポピュラー音楽がいかに商業的にリードされてきたかを説明している。また、レコード会社、広告代理店、芸能プロダクションの関係が構築されていった経緯も分かるので力関係が分かるようで分からない芸能界の構図も少し分かったような気がしてくる。また、この構図が音楽づくりにも影響を与えていく。2023/11/21
山口透析鉄
23
以前、ざっと図書館本で読みました。 音楽家そのものとしてどの程度のものか?というような評価はとりあえず置いといて、日本のポピュラーミュージックの全貌が新書の範囲でよく分かるようにまとめられていました。 著者、元朝日新聞記者でAERA編集部にもいましたので、当時の経験も役に立っているのでしょう。 別の場所では椎名林檎さんを非常に高く評価されていたのも印象に残っています。
しゅん
10
産業としての日本大衆音楽の記述としてはデータとトピックの扱いがしっかりしていて参考になる。読んでて楽しいし。J-POPの盛り上がりにアメリカにいた経験が活きている感じする。カラオケ産業の歴史が細かく書かれててて面白かった。90年台の一番売れていた頃のエイベックスが創業10年に満たないガチの新興レーベルだと知ってビビった。政治絡みの音楽事務所不祥事の連鎖は、先のオリンピックまで繋がっている話。この本がゼロ年代っぽいなと感じる理由はなんだろう。2021/11/17
にゃん吉
9
Jポップという言葉の由来から始まり、録音技術の変容、媒体、再生装置の普及等の技術的な事情、テレビとのタイアップ等々の売る側の事情、カラオケの隆盛、渋谷文化(「渋谷系」の音楽)等々の現象から読み解かれる自己表現、自己愛的嗜好という消費者側の事情、輸入超過、内需型で巨大な日本の音楽市場の実情といった種々の要素が指摘、分析され、Jポップを生み、育てた本邦の音楽産業、社会の構造が明らかにされています。非常に面白い一冊。平成17年頃の著作なので、その後の「Jポップ」を分析した本があれば、それも読んでみたい。 2021/04/24
ミヤト
8
Jポップの誕生から最盛期、そして……といったJポップ史を描く。打ち込みの音楽の登場・着メロの普及など、音楽界を取り巻く環境の変化がJポップの傾向にすくなからず影響を与えているのだとわかった。2022/09/12


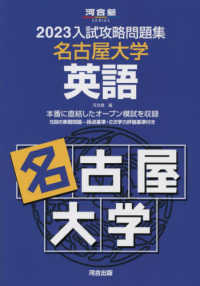

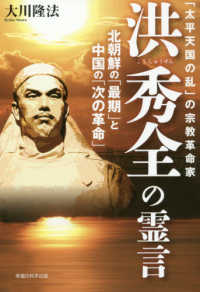
![文様切り型 [ガジェットブックス シリーズかたち] [バラエティ] (新版)](../images/goods/../parts/goods-list/no-phooto.jpg)