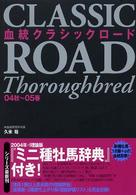出版社内容情報
日頃は意識されにくい存在だが,かつての「西暦2000年問題」のように,一度トラブルが起きれば社会機能が麻痺するほど重要なのがソフトウェア.システムの基礎から違法コピー問題まで,意外に知らないソフトウェアの現在を解説.
内容説明
外は変わらないのに中身を替えればすっかり新しい機械になる。当然のようだが以前の機械には考えられないことだ。これがソフトウェアの威力である。空気と同様、日頃はほとんど意識されないが「西暦二〇〇〇年問題」や「ウイルス問題」では、その存在感もアピールした。意外に知らないソフトウェアの現在を、基本からやさしく解説。
目次
1 ソフトウェアとは、システムとは(コンピュータについて;プログラム内蔵方式計算機 ほか)
2 ソフトウェアの現場で(隠れたソフトウェアと固いソフトウェア;ソフトウェアに関わる人々 ほか)
3 試練の中のソフトウェア(ネットワークの衝撃;ソフトウェアのハード化 ほか)
4 ソフトウェアの将来像(重要性が増す一方、労働市場縮小の危険も;ソフトウェアの新しい形 ほか)
著者等紹介
黒川利明[クロカワトシアキ]
1948年大阪に生まれる。1972年東京大学教養学部基礎科学科卒業。同年東芝入社、82~85年新世代コンピュータ技術開発機構へ出向。85年日本アイ・ビー・エム入社、89~90年IBM T.J.ワトソン研究所、99年CKS入社。専攻はソフトウェア科学。現在、(株)CSKフェロー、eソリューション技術本部勤務
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
63
1992年のかかれたものですので、内容はかなり古くて実際にはあまり役にはたたないと思われます。ただコンピュータの中でのソフトウェアの立ち位置やどのように使うか、また人間の文化との係わり合いの箇所などは今でも参考になると思い読み返しました。新しい改訂版を出してくれないですかね。2015/09/29
茶幸才斎
4
ソフトウェア、プログラム、システムといった言葉の意味について、ソフトウェア開発の方法について、また本書の出版当時の重要テーマであったネットワーク時代におけるソフトウェアのありようや、今なお重要テーマである信頼性の問題について解説するとともに、ソフトウェアに関する技術研究の発展がもたらす将来像について展望している。古い本であるが、「情報システムは作られただけでは価値はなく、運用されて初めて価値が生じる」とか、「システム開発で重要なことは何を作らずに済ませるかだ」とか、今読んでも示唆に富み、はっとさせられる。2017/07/18
m!wa
3
プログラマー不要説は一理あると思う。東南アジアのエンジニアが日本の開発を引き受けないのは、日本語の壁があるっていうのは、確かにそうだと思う。海外にやすいお金で発注しても、期待どおりのものができてこなくて、あとで日本人が修正するっていうのは、もうやめにしたいなぁ。2014/07/09
rubix56
3
どちらかというと、技術的なことではなく、ソフトウェアの歴史、未来像を2002年現在とし、記しているものと考える。 何か、ブログラミングを身につけたいなら、お門違いである。 2012/03/05
若
2
もうちょっと勉強してからまだ再読したい本。2011/06/10