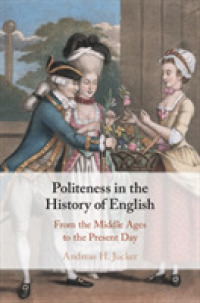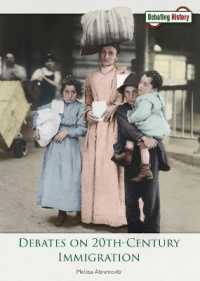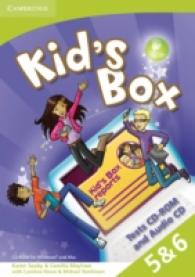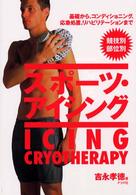出版社内容情報
ドキュメンタリーで社会の現実を,ドラマで虚構の物語を映像化する際に,何が壁となり,どんな冒険に挑んだか.NHKの看板ディレクターとして斬新な番組づくりを重ねた著者が,映像表現の可能性と重層性,その危うさを語る.
内容説明
ドキュメンタリーで日本と世界の現実を、またドラマで虚構の人間模様を映像化するにあたって、何が壁となり、どんな冒険に挑んだか。NHKの看板ディレクターとしてテレビの草創期から斬新な手法と大胆な構想力で開拓的な番組づくりを重ねた著者が、自らの体験を回想しながら、映像表現の豊かな可能性とその危うさを語る。
目次
獅子吼する教祖―撮るべきものが撮れるか
すべては白紙から―映像はひとり歩きする
「素材」としての賭場―撮りたい理由、撮らせる理由
考えるカメラ―日本人のメンタリティに迫る
潜伏キリシタン―訴える人びと、終わらない歴史
ボツになった「無残絵」―「茶の間に出せぬ」映像とは
乱舞する巴文―楽譜か神火か人魂か
推定有罪―ドキュメンタリーの怖さを知る
歴史上の人物―「時代劇」から「歴史ドラマ」へ
香水の匂う刃物―芝居と芝居のインターラクト?
じかに見せろ―視聴者の注文に応えられるか
カメラと活字の距離―映画が手をつけなかった領域へ
なぜ現在かくあるのか―欧米にさぐる未知の風景、歴史の刻印
映像にとって廃墟とは―現在と過去のモンタージュ
〈映像化〉とは何だろうか―現実の重層性を引き出す
心に火をつける―「あとがき」をかねて
著者等紹介
吉田直哉[ヨシダナオヤ]
1931年東京に生まれる。1953年東京大学文学部西洋哲学科卒業、NHK入局。ディレクターとして、本書でとり上げられているドキュメンタリー・シリーズ「日本の素顔」『新興宗教をみる』(1957年)、同『日本人と次郎長』(1958年)、同『隠れキリシタン』(1959年)、「東南アジアをゆく」(1960年)、『日本の文様』(1962年)、『TOKYO』(1963年)、大河ドラマ『太閤記』(1965年)、同『源義経』(1966年)、ドキュメンタリー・シリーズ「海外取材・明治百年」(1968年)、同「未来への遺産」(1974‐75年)、同「21世紀は警告する」(1984‐85年)、「ミツコ―二つの世紀末」(1987年)などを制作。芸術選奨文部大臣賞、日本記者クラブ賞などを受賞。専務理事待遇ディレクターを経て退職後、1990‐98年、武蔵野美術大学映像学科教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しんこい
南註亭
shushu
kyoko
takao