出版社内容情報
現代の教育を考えるとき,その背景にある企業社会,高度情報化社会を視野に入れないわけにはいかない.いじめや落ちこぼれなど様々な深刻な問題を生んでいる社会の構造を明らかにしながら,歴史をどう教えていくか,核や環境の問題をどのように自らの課題として引き受けていくかなど,これからの教育のあり方について未来を見据えつつ明確な指針を与える.
内容説明
現代の教育を考えるとき、その背景にある企業社会、高度情報化社会を視野に入れないわけにはいかない。いじめや落ちこぼれなど多くの深刻な問題を生んでいる社会の構造を明らかにしながら、歴史をどう教えていくか、学校のなかでの能力主義・競争主義や教育の商品化をどのように考えるべきかなど、様々な問題について明確な指針を与える。
目次
序章 過去を心に刻み未来への希望を紡ぐ―戦後五〇年を振り返って
第1章 現代企業社会と学校・家族・地域
第2章 現代社会と教育―「能力主義」の問題性
第3章 学校の現在と学校論
第4章 ゆらぐ学校信仰と再生への模索
終章 教育改革を考える
著者等紹介
堀尾輝久[ホリオテルヒサ]
1933年福岡県に生まれる。1955年東京大学法学部卒。専攻は教育学・教育思想史。現在、中央大学教授、東京大学名誉教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
客野
2
1、3章は示唆に富む。他の章は、部分的には興味深い指摘もあるものの、全体として見ると、特に2章は素朴に過ぎる主張だと思う。堀尾の研究の、歴史から教育を見るところは素晴らしいと思うが、現代の分析は黒崎勲に遠く及ばない。2017/07/24
そうげん(sougen)
1
《日本社会は一見平和に見えて、管理と競争のシステムのなかにあり、学校もその例外ではない。体罰といじめの問題は、まさしく直接的暴力の問題であり、陰湿ないじめや内申書による抑圧は構造的な暴力の問題でもある。いずれにしろ、現在の学校に支配的な文化は「平和と人権の文化」の対極にあるものだといわねばならない。》(237p.)本書の上梓されたのが1997年。当時とくらべ、現在、教育の現場、そして日本社会はどう変わったんだろうか。2022/04/17
-

- 電子書籍
- 妖魔狩りの末裔-俺だけ不死身の覚醒者-…
-

- 電子書籍
- Dragon Beauties 霖霖 …
-
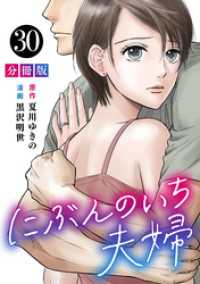
- 電子書籍
- にぶんのいち夫婦【分冊版】30
-
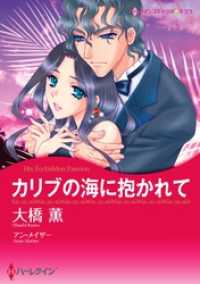
- 電子書籍
- カリブの海に抱かれて【分冊】 4巻 ハ…
-
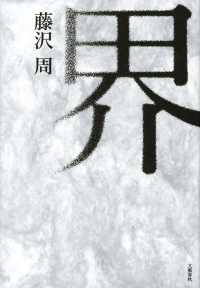
- 和書
- 界




