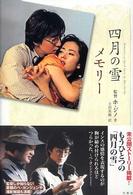出版社内容情報
冷戦が終結し,米ロの「核」は大半が,もう必要ないものとして,実質的にも社会的にも解体され始めた.しかし今,核保有の危機は,世界中にひろがりつつある.また,密かに流出する核物質.各地で勃発する民族紛争との結び付きもささやかれている.核の現況を,長年の取材と最近公開された文書によって明らかにする迫真のルポ.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ユ-スケ
4
あらためて、の核問題なのだけど、人類は実に無駄なものを作ってしまったものである 時間とお金、そして頭脳を使って開発し、でも使えない・・ これって究極の無駄だよな 人間ってほんとにバカだよな って20年近く前の本書を読みながら思っているときにICBM発射だよ あああなにも学んでない・・・2017/08/03
茶幸才斎
2
米ソ冷戦期の核抑止理論により核軍拡競争が加速したが、80年代に入るとその過大な経済的負担が重荷となり、核軍縮に向かう。米ソの核解体が進む一方で、冷戦後は核拡散の防止と厳格な核管理に世界が腐心するようになる。本書は、こうした核兵器の拡大、縮小そして管理の変遷を、国際政治の歴史から解説した後、更に核廃絶を実現するシナリオをも提示する。しかし、複雑怪奇な現実の国際情勢を思えば、その道のりは遠そうだ。核をいかに「割に合わない代物」に変えられるかが鍵であるが、一度発明されてしまった技術は、滅多なことでは消滅しない。2012/08/02
ゆきまさくん
1
冷戦が終わった直後は、米露の軍縮交渉が進み核は必要がないものと思われ、解体が進められた。しかしながら、相も変わらず核抑止論が唱えられた。それは、見えない敵への核保有の正当化、大国の地位保全、不確実性への対応によるものだという。 さらには原発によるプルトニウムの平和利用や地域問題の観点から、むしろ核は拡散していった。 つまり核保有を前提とした国際政治の情勢から、核依存の体質を変えられなかったという。 この状況は時間を経た今となっても何ら変わらない。2019/05/14
チャリ男
0
ICBM、SLBM、原爆と水爆と中性子爆弾をググって調べてしまいました。2010/02/02