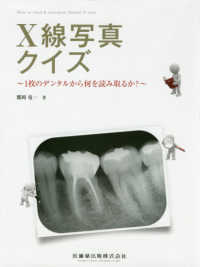出版社内容情報
一九八九年秋,相次ぐ共産党支配の崩壊という未曾有の政治ドラマのさなかに,各国の権力中枢ではどのような論理と思惑が交錯し,党の幹部たちはどうふるまったか.劇的な変動のあとにやってきたのは何か.現地取材で得られた多数の証言をまじえて「革命」の真相に迫る.混迷する東欧のゆくえを見定め,社会主義の命運を考える上で必読の書.
内容説明
一九八九年秋、相次ぐ共産党支配の崩壊という未曾有の政治ドラマのさなかに、各国の権力中枢ではどのような論理と思惑が交錯し、党の幹部たちはどうふるまったか。劇的な変動のあとにやってきたのは何か。現地取材で得られた興味深い証言をまじえて「革命」の真相に迫る。
目次
1 分断国家と革命―東ドイツ
2 マジャール党の革命―ハンガリー
3 思惑超えた議会革命―ポーランド
4 バルカン宮廷革命―ブルガリア
5 遅れてきた「プラハの春」―チェコスロバキア
6 乗っ取られた革命―ルーマニア
終章 「東欧」の消滅
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
60
こちらは二人のジャーナリストによるもので、1992年末の出版なので一段落したあとのもの。ソ連と同盟関係になかったユーゴとアルバニア以外の共産党崩壊過程をコンパクトにまとめている。『'89・東欧改革』が緊急出版的でしかも研究者のものであるため、やや著者の立場が見え隠れするものもあったが、こちらは冷静かつ読みやすい。チェコスロヴァキアは分裂の端緒の動きまで書かれている。特筆すべきはルーマニアの章で、チャウシェスク処刑までの民衆の動きは党と軍内の反対派の策謀があった可能性を強く示唆、党内の権力闘争と見立てる。2023/12/21
ふぁきべ
9
かなり古い本だが、旧共産圏6か国における非共産化革命をまとめた一冊。ちょうど欧州旅行中に読んでいたこともあって、ベルリンの壁を眺める気持ちによりリアル感覚を持たせてくれた。少しぎゅうぎゅう詰めな感もあり読みにくさを感じなくもなかったが、革命が起きたときにその場にいたようなリアル感を感じさせる。当然その後の考察のような部分は古さを感じさせるが、それは後世を生きる我々がオチを知っているからであって著者たちの責任ではない。本書に登場する中で訪れたことがないのはルーマニアとブルガリア、ポーランドなので来年こそは。2023/08/11
うえ
6
あくまでも東ドイツあるいは、統一ドイツをNATOに加盟させないという「ソ連」との話が、何故だかウクライナにすり替わっていく前段階の事情。1990年のワルシャワ条約機構での会議「シュワルナゼは統一ドイツのNATO帰属に反対する演説を行ったが、ハンガリー外相、チェコ外相らがこれに反論…シュワルナゼは謝意を示した。…つまり、ソ連側に経済支援を与える見返りに、ソ連側はドイツ統一を妨害しないという取り引きだった。…統一ドイツのNATO加盟がソ連に与える心理的インパクトを除去することも重要だった。」2025/04/05
ゆーじ
2
相次ぐ共産支配の崩壊は社会の営みに人権や自由が絶対に必要だという事を証明した。全体主義国家のロシアや北朝鮮、中国なども必ずや自由主義国家に変わるはず。国民を不条理に押さえつける事は絶対にできないし、あってはならない。東欧諸国の変遷をみて怯えているのだろう、ロシアの支配者は。2024/02/19
hutaketa
1
[試験対策本Ⅰ]東欧(とバルカン地域)の本質は複雑さである、と思う。だから1989年の政変を、単に「歴史のうねり」として片付けることはできないし、民主化・ナショナリズム・共産主義の崩壊という視点でのみ語るのも間違っている。東欧を理解するにはミクロの視点が必要不可欠だ。例えば政治プレイヤー。この本は彼らの「権力移行プロセス」に注目することで、東欧革命という現象に肉薄している。古い本だが終章での問題提起(東欧の二極化、民族問題)は現代に通じるものがある。この内容を踏まえてポピュリズムの問題にも取り組みたい。2010/12/22