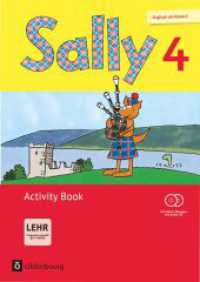出版社内容情報
世界一の長寿国となった日本.だが一方で,「老い」への不安もまた大きい.中高年,特に老人は,「ぼけ」や「寝たきり」に代表されるように,ただ衰えていくだけの存在なのだろうか.本書は心理学の立場から加齢と知的能力との関連を探り,人間はそれぞれの年代において常に有能であり続けると主張して,「老化」の見方を大きく覆す.
内容説明
世界一の長寿国となった日本。だが一方で、「老い」への不安もまた大きい。中高年、特に老人は、「ぼけ」や「寝たきり」に代表されるように、ただ衰えていくだけの存在なのだろうか。本書は心理学の立場から加齢と知的能力との関連を明らかにし、人間はそれぞれの年代において常に有能であり続けると主張して、「老化」の見方を大きく覆す。
目次
序章 発達の可能性への挑戦
第1章 エキスパートになる
第2章 充実した中高年期
第3章 知的能力はいつ衰えるか
第4章 愛情のネットワーク
第5章 かけがえのない「私」
第6章 子どもの思考・おとなの思考
第7章 無力だが有能
第8章 三つ子の魂百までか
第9章 さまざまな学びの場
第10章 老いを支える
終章 発達観を問い直す
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
紫羊
20
1990年末に出された本だが、私が買ったのは2013年5月の第28版。息長く読み継がれている名著だと思う。「人間の発達は柔軟で、取り返しがつかないということはない。」という著者の言葉は、これから高齢期に向かう私にとって力強いエールに聞こえる。2013/10/16
壱萬参仟縁
15
中高年が老いる中で、ポジティヴに生きるにはどうしたらいいのか。そんな時代に突入している。50歳前後が中年期のようなので、まだ先なのか。少し安心したが、失われた30代であるので、失われた40代にならないようにせねば。中年の生活には個人差が大きい(36頁)。とりわけ、格差社会で家族、兄弟でも人生格差である、妻子の有無、定職の有無という形で顕在化しているのである。知的能力はまだ伸びる余地がありそうなので(56頁~)、これも安心した。格差が顕在化する中年だが、人と比べる必要なし。同じ境遇で比べるのには意味がある。2013/08/15
riviere(りびえーる)
7
人は生涯発達し続ける。今はさほど驚かないが、この本が発刊された当時なら、この本を読むことで救われた人がいたことだろう。例えば三歳児神話のために子育てに緊張していた親たち、ある一定の年齢が過ぎたら人は衰えるだけなのだと思っていた中高年。人生はいくらでも、そしていくつになってもやり直せる。2012/11/20
生ハム
2
「学ぶ」ことは何も学生だけの特権ではないのだと改めて思わされた一冊。今後さらに、色々な世代の人が学べる環境が整ったらいいなあと思います。特に、中高年の発達の様子を視野に入れて、学校教育をとらえ直すというのは面白かったです。 やはり学校教育は特殊な場ですよね。 中高年にとって、学校が意味ある存在になったら素敵なことだと思います。 中高年は、PCで言うならハード面は進化しないけれど、 ソフト面は進化できるんですね。 むしろ、経験があるぶん、より有能であるのは疑いようがない。2012/10/01
読書サクサク
2
流動性知能は青年期の前から次第に低下していくが、結晶性知能は青年期を過ぎてもなお緩やかに発達し続けるとは、知らなかった。そして、中高年が有能さを保つためには三つのことが必要。一つは何らかのエキスパートであること。二つ目は健康であること。三つ目は社会的サポート。たとえば、よい家族や友人に恵まれることや、経済的ゆとりが必要なのだそうだ。それらに注意して、今後の人生の午後を過ごそう。2013/08/28