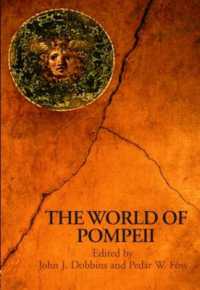出版社内容情報
自然破壊,核の脅威など人類が直面している課題に対して,教育は有効な営みとなっているのだろうか.地球上に美しい水や空気を取り戻し,虫や獣とも共存できる生き方を実現するために,教育に何ができるのか.子どもと若者の未来に強い関心を抱く著者が,祖先からの子育ての知恵をも振り返りつつ現代における教育の意味と役割を問い直す.
内容説明
自然破壊、核の脅威など人類が直面している課題に対して、教育は有効な営みとなっているのだろうか。地球上に美しい水や空気を取り戻し、虫や獣とも共存できる生き方を実現するために、教育に何ができるのか。子どもと若者の未来に強い関心を抱く著者が、祖先からの子育ての知恵をも振り返りつつ現代における教育の意味と役割を問い直す。
目次
第1章 子育ての意味―種の持続のために
第2章 人の子育て―一人前ということ
第3章 ヒトが人になるとはどういうことか
第4章 人間の可能性はどこにあるのか
第5章 ヒトが人であるために
第6章 文化の中で育つ
第7章 いま教育は―臨教審との出合いの中で
第8章 人権としての教育
著者等紹介
大田堯[オオタタカシ]
1918年広島県に生まれる。1941年東京帝国大学文学部教育学科卒業。専攻は教育史・教育哲学。現在、東京大学名誉教授・都留文科大学名誉教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りょうみや
11
1990年の本だが出てくる今でも十分通用する内容。教育環境が直面している問題が30年前と現代とほぼ変わりがないことに驚く。教育・子育てを生物学的な観点から捉え直しているのがよい。本筋に沿っていそうで微妙に外れている寄り道ばかりの本。個人的にはエリクソンの発達理論の教育への有用性の裏付けになった。2018/04/24
Ryo Hirao
7
動物と人間を対比して「子育て」を考えることから始まり、人間としての教育のあり方や現代的な問題に至るまで広く「教育」を扱う。小規模な章を重ねて話を進めていく形式になっており、読みやすくわかりやすい。初版は四半世紀も前の1990年だが、多くの問題が変わらず残され続けていることにも気づかされる。制度としての教育、教育者の考えるべき教育など多くの視点で読むことができ、教育に関わる仕事をしたいと考える人には、その職の種類にかかわりなく広く読む意味のあるものとなっている。2015/05/30
さわ
2
筆者のエッセイから始まり、動物生態学の話になるなど、タイトルの偽りがあるのかと思った。が、後半になるにつれて、教育とは子供が学び、自分自身の持っている能力を発揮することだと論じる。そして、子どもが大人になり、社会を構成していくことが大事だと主張している。2016/10/07
スズツキ
2
題に対して蛇行が多くて、欲しい情報があまり得られなかった。2014/02/15
_udoppi_
2
教育の本質は「種の保存」。社会を持続、発展させるため、人間存在の相互依存性(社会性)を前提としながら、他者とかかわり合いながら一定の社会的役割を果たせるような自立した「一人前の」人間を形成するために教育はある。教育は本質的に公共的publicで、現在その責任は憲法上国家が負うことになっているが、教育は同時に一人ひとりの個性的な分別力(本書曰く「わきまえる力」)や目的意識を発展させるものでなければならない(personal)。競争主義的教育に疑問が差し挟まれなくなって久しい今こそ自由主義的教育復権の時では。2012/12/04
-

- 電子書籍
- 暴君パパに殺されかけたけどハッピーエン…