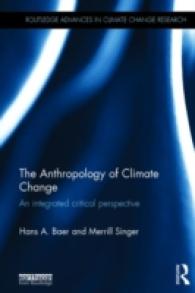出版社内容情報
子どもがことばを話しはじめる.これほど愛らしい光景はないが,その内部では,ことばを獲得するための激しい戦いが繰りひろげられている.子どもはある時点に至らないとなぜ話しはじめないのか.ことば以前のコミュニケーションに注目し,どのようにことばが生み出され,そのことばが子どもの発達をどう方向づけるかを語る.
内容説明
子どもがことばを話しはじめる。これほど愛らしい光景はないが、その内部では、ことばを獲得するための激しい戦いが繰りひろげられている。子どもはある時点に至らないとなぜ話しはじめないのか。ことば以前のコミュニケーションに注目し、どのようにことばが生み出され、そのことばが子どもの発達をどう方向づけるかを語る。
目次
はじめに 発達のなかのことば
1 ことば以前(新生児のコミュニケーション;発達の場における「人」の機能 ほか)
2 シンボルの形成(記号の世界;音声の機能 ほか)
3 ことばの獲得(ことばの機能と子どもの発達;自我の形成とことば ほか)
おわりに 三つのエピソードから
著者等紹介
岡本夏木[オカモトナツキ]
1926年京都に生まれる。1952年京都大学文学部哲学科卒業。専攻は発達心理学。現在、京都女子大学教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みき
20
子どもの言語獲得の過程を記した一冊。 言葉は人格形成に深く関わり、自分と他者をつなぐものでもある。それを子どもが自由に操れるようになるには、多くの苦闘や成長があって成し得ることだという。これを研究することで、言葉の重要性、人間性とは何かを考えることにつながる。 言葉や自我は苦難に陥ったときに自分自身を励ますのに役に立つ、という部分に感心した。また、気持ちや経験を言葉で交わして共有することの大切さを改めて認識した。 この本は自分にとって今までの成長を省みてこれからどう繋げるか、手がかりになりそう。2017/09/08
ふろんた2.0
11
ことばの発達に関する本なら今井むつみさんの方がわかりやすくて面白かったな。2015/10/07
Nobu A
5
岡本夏木先生著書2冊目。1982年初版の黄版が時代を物語たり、2004年第39刷の発行部数から人気ぶりが窺える。個人的には前著「幼児期」に大きな感銘を受けただけに期待値が高過ぎた。本著にも随所に研究者としての矜恃や示唆に富む表現があったが、逆に言うとそれまで。発展を遂げつつある子供の機能や領域は相互に不可分な形で結び合い連関しあって発展していくものと考えると、子育てとは共有出来る掛け替えのない経験。言語獲得の一方で、情報処理や表現形式は機械的に固定化されやすい。その結果、感性や想像力が鈍る可能性がある。2022/04/12
Akiro OUED
5
指差しをする=発語する。シニフィアン・シニフィエ。著者が、コミュニケーションを拡大解釈する理由が理解できた。自己を認識することは、他者を識別できた後にやってくる。ならば、文字を使わずに、イメージだけで意思疎通する電脳空間では、自己の同定ができなくなる可能性が高い。名著。2021/11/26
半兵衛
5
子供が言葉を操り始めるまでの概論。子育て中の人間にはあるあるなことが書いてある。1982年の本だが古臭さはなく読みやすい。知っていた事実や経験の確認、と思っていたら「おわりに」の終わりで泣いた。わがものとしてこそのことば。2021/08/04
-

- 電子書籍
- 百十三代目の司書見習い
-
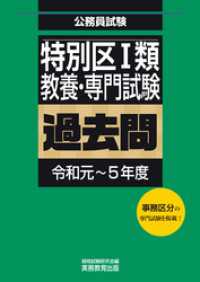
- 電子書籍
- 特別区1類 教養・専門試験 過去問(令…