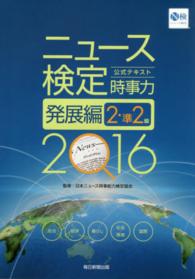出版社内容情報
朝永 振一郎[トモナガ シンイチロウ]
著・文・その他
内容説明
現代文明を築きあげた基礎科学の一つである物理学という学問は、いつ、だれが、どのようにして考え出したものであろうか。十六世紀から現代まで、すぐれた頭脳の中に芽生えた物理学的思考の原型を探り、その曲折と飛躍のみちすじを明らかにしようとする。本巻では、ケプラーから産業革命期における熱学の完成までを取り上げる。
目次
ケプラーの模索と発見
ガリレオの実験と論証
ニュートンの打ち立てた記念碑
科学と教会
錬金術から化学へ
技術の進歩と物理学
ワットの発明
火の動力についての省察
熱の科学の確立
著者等紹介
朝永振一郎[トモナガシンイチロウ]
1906年‐1979年。1929年京都大学理学部卒業
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
molysk
45
朝永振一郎は、物理学者。ノーベル賞受賞。一般向けの著述家としても有名で、本書で大佛次郎賞を受賞。物理学とは何か。まずは「自然界のもろもろの現象の奥に存在する法則を、観察事実に拠りどころを求めつつ追及すること」と定義して、物理学的思考の発展を明らかにしていく。上巻の対象は、主に古典力学と熱力学。古典力学は、ケプラーの惑星観察およびガリレオの動体実験を、ニュートンがニュートン力学として確立する。熱力学は、カルノーによる熱と動力の変換の考察から、クラウジウスのエントロピー、ケルビンの絶対温度へと進展していく。2020/06/21
おつまみ
45
数学と物理学。関係が深い割りに、実際に学ぶとその距離は遠い。技術者からしたら数学は道具だが、学問として哲学。2019/08/16
nbhd
22
この本を読みながら思ったのは、「物理」って興味をもつのがなかなか難しいのではないかということだ。宇宙が気になる!とか、アインシュタインってどんな人?とか、初めに素直な気持ちがあるとよいのだけど、そういうのがないと、数学が混じっているから難しそうとか、高校物理の初っ端でv-tグラフとか、感動と興奮があまり伝わりそうにないというのが率直なところだ。この本でいうと、僕はまだ熱力学で興奮できるところまでいってない。世界は不思議だなって感じる心を育むのはむずかしい。熱力学で興奮できるようになりたいな。2021/06/14
ひろ
18
ケプラーやニュートンを「公式や法則の一部として」ではなく「歴史的な背景や他学問との繋がり」を意識しながら物理学を俯瞰できる一冊。物理は学校で学ぶとどうしても公式が先行してしまうけれど、本質を理解するためにはこうした本をまずは読むべきだと、今更ながら思った。一部を除いて数式を殆ど使用せず、ですます調で易しく諭す書き方で、びっくりするほど読み易い。斎藤孝さんの「読書力」で紹介されていて知った本だけど、間違いなく名著。2014/01/26
ベンアル
16
図書館にて借りた本。ケプラー、ガリレオ、ニュートン、カルノーと時代を追って物理学について説明している。ケプラーはすべての惑星が太陽を中心に長円上に回っていること、面積速度が一定であること、ガリレオは等速運動、等加速度運動、ニュートンは万有引力や物理学の数式化を発明した。第一章の力学はついていけたが、第二章の熱になってから内容が難しくなってきた。2022/08/27




![Kyoto Classification of Gastritis - 胃炎の京都分類[英語版]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48887/4888752982.jpg)