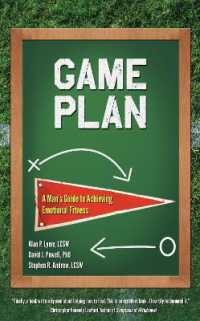出版社内容情報
芭蕉の句「古池や蛙飛びこむ水のをと」の主役は音である.閑寂の緊張をとらえ,動の中に静をとらえて充足する耳.民族はその耳にふさわしい音を選びとり,固有の音の世界を形づくる.話しことば,手足の動き,楽器など,あらゆる生活領域に向けられた鋭い観察を通じて,日本独特の音の世界を抽出し,独自の日本文化論,音楽論を展開する.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ふう
4
仕事で必要に迫られての再読です。古い本ですが、視点は今読んでも新鮮。面白かった。2015/09/22
:*:♪・゜’☆…((φ(‘ー’*)
3
着想点と描写力が素晴らしい(^^)農耕民族は、田畑を荒らさぬよう大地にそっと足を下ろすようなエコな動きや一旦停止の運動、馬に乗る民族はアレグロの躍動感。体にしみついたリズムが言語にも表れていると。奈良時代の日本語は8の母音と今と異なる音(サ行ts、濁音dz、チとツのt、ハ行のf)があったと。万葉集をまんにょうしゅうと読んでいたなど聞くと、実際の音で歌をきいてみたくなる。「たとえば『~n-nyo』に見られる重なり合ったnは、今日僕らがおおむねハミングで済している「ン」と相違した、深いnの響きを思わせ、yも…2022/04/15
RYU
2
昭和時代の作曲家による日本文化論。日本人の耳は、閑寂の緊張をとらえ、動の中に静をとらえて充足する耳。日本の音楽は、しじまさえ聞く、間(ま)の音楽。リズムの取り方は、手と足の使い方(摺り足など)や、舌と唇の使い方(息の切れ目=音の切れ目)などに現れる。引用された角田忠信氏の論文によれば、母音・人の声・虫の音・鳥や獣の啼き声は、日本人は言語脳で処理し、外国人は音楽脳で処理する。2017/08/06
yurari
0
これは面白い。日本人特有の、音に対する感受性。勉強になりました。2014/01/11
-
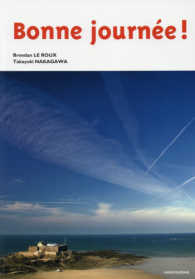
- 和書
- ボン・ジュルネ!