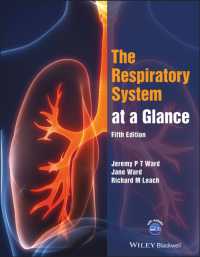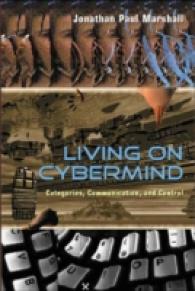出版社内容情報
学校では知識は教えるけれど知識の獲得のしかたはあまり教えてくれない.メモのとり方,カードの利用法,原稿の書き方など基本的技術の訓練不足が研究能力の低下をもたらすと考える著者は,長年にわたる模索の体験と共同討論の中から確信をえて,創造的な知的生産を行なうための実践的技術についての提案を試みる.
内容説明
学校では知識は教えるけれど知識の獲得のしかたはあまり教えてくれない。メモのとり方、カードの利用法、原稿の書き方など基本的技術の訓練不足が研究能力の低下をもたらすと考える著者は、長年にわたる模索の体験と共同討論の中から確信をえて、創造的な知的生産を行なうための実践的技術についての提案を試みる。
目次
1 発見の手帳
2 ノートからカードへ
3 カードとそのつかいかた
4 きりぬきと規格化
5 整理と事務
6 読書
7 ペンからタイプライターへ
8 手紙
9 日記と記録
10 原稿
11 文章
著者等紹介
梅棹忠夫[ウメサオタダオ]
1920年京都市に生まれる。1943年京都大学理学部卒業。京都大学人文科学研究所教授を経て、現在、国立民族学博物館名誉教授・顧問。専攻は民族学、比較文明論
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ehirano1
161
約10年ぶりの再読。10年前読んだ時は、どうしてもっと早く本書と出会えなかったのかと思うくらい感嘆したのを久しぶりに思い出しました。約10年の時を経て、本書で紹介されている幾つかを亜流ながら自身が使用していることになんだか妙に懐かしを感じながらの読書となりました。そういえば、KJ法を知ったのも本書からでした。2024/01/07
mukimi
118
「整理は機能の秩序、整頓は形式の秩序」「知的生産の技術で情緒の乱流を取り除き秩序としずけさを取り戻す」「日記は自分という他人との文通」「本好きの読み下手」など、半世紀以上読み継がれるに値するシンプルで魅力的な言葉が並ぶ。外山滋比古氏のベストセラー「思考の整理術」も、紙に書いて書いて書きまくり取捨選択し整理する手法であり共通しているようだ。タブレットやアプリを使いこなせくて焦るけど、私は自信を持って紙で知的生産していこうと思えた。でも令和時代の電子機器による知的生産技術、誰か体系的に纏めてくれたら読みたい。2024/04/29
ねこ
78
京大名誉教授、民族学者、情報学者、未来学者、…など多才な梅棹師の著書。若かりし時代から、ご年配までの写真を拝見しましたが、どの年代であっても精悍で且つ優しさと知性が滲み出ていますね。半世紀前からの先達の努力の積み重ねで現在、能動的で、かなり完成された個人の情報管理が安価で享受できるに至ったのだと私は感じました。野外科学に於いて、その場で観察と記録のずれは短いほどよろしい。と有りましたが、野外科学に限らず私は自分の考えや発想を記録する努力が足りない事も痛感しまた。最後に万年筆で手紙を書いてみたくなりました。2022/02/01
崩紫サロメ
74
50年以上前に出版された本書、何度も読み返しているのだが、様々な技術革新があっても古くならない部分は何なのか。それは内容至上主義を否定し、形式を与えることによってこそ、ひらめいた発想が活かされるというところではないか。ひらかなタイプライターのように、歴史的な存在となってしまった様々な道具が登場するが、それらを使うことによって何を目指したのか。著者は「情報をたいせつにする」ためにきちんとしたしつけが必要であるという。当然これは現在にも言えること。具体的にどのようにすればよいか、いろいろと刺激をもらえる1冊。2022/01/16
TomohikoYoshida
62
自分が生まれたころに書かれた本を、半世紀以上経ってから読む。100刷されただけあって、とにかく面白い。最初は、ノートからカードへの道具の発明と進化の話。情報をいかに活用しやすく分類・整理・整頓するためのツールとテクニック。そして、ペンからタイプライターへ。今はPCやタブレットでペンよりもきれいに早く文字が書ける時代が来ている。しかし、文章を書く時の考えのまとめ方や、文章の書き方というものは普遍的だ。考えをまとめるツールとしてマインドマップや付箋なんかは結構便利に使っているなと思いながら読んだ。2020/09/10
-

- 電子書籍
- ヒミツのヒロコちゃん【マイクロ】(17…