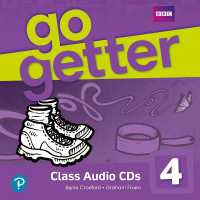出版社内容情報
異教徒からの聖地エルサレム奪回の名の下に,十一世紀末から十三世紀後半にかけて,キリスト教徒による遠征がくり返し行なわれた.その実態はどんなものであったか.彼らはいかなる動機でどのような過程をへて東方に向ったのか.イスラム側はそれに対してどう反応したか.その理想と現実の姿を明らかにし,従来の聖戦観の打破を試みる.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みなみ
13
十字軍について、気候変動や人口動態の変化といった社会変動から語り明かしていく一冊。この時期の西ヨーロッパから外に向かう信仰のエネルギーは、聖堂建築ブームラッシュや、聖地巡礼の旅という形を取る。巡礼に赴いたのは、ある程度収入が安定した社会層。巡礼を旅ブームとみれば江戸時代の日本と比べたくなる。さて最初は巡礼者として歓迎された十字軍は、エルサレムの虐殺行為により敵視される。ユダヤ人を会堂に閉じ込め焼殺するのは後のナチスの原型と指摘される。西洋の聖戦意識は十字軍だけでなく近現代まで広げて捉えるべきか。 2021/04/10
水無月十六(ニール・フィレル)
6
十字軍という「現象」について、当時の社会情勢や人口動態、気候変動など多角的な視点から分析し、歴史を追いつつ記述された本。十字軍の戦闘行為は「正戦」感に貫かれていたと読み取れる内容だった。そもそもその考え自体が後付けなのでは無いのだろうか。民衆の行動は宗教的情熱に感化されたとして、軍事行動を行なった諸侯の間に、最初から宗教的な意思はあったのだろうか。ひいては呼びかけを行った教会にその意思は最初からあったのだろうか。「正戦」を持ち出すにしても根拠とする事件は時代が離れていないかなどの疑問をさらに深めたい。2016/12/07
讃壽鐵朗
4
歴史映画の大作「キングダムオブヘブン」を見てから読んだせいもあるが、単なる歴史書ではなく、実に物語性のある書き方で、十字軍の実態がよく理解できた。2015/01/16
mcpekmaeda
2
「できるだけ紙幅をさいて原典に語らせる形式」と著者自らが、あとがきで書く通り、十字軍を研究した文献からの豊富な引用が特徴となっている。1974年の本なので、十字軍を語るにおいて、人類史において肯定せざるべき、「戦争」について考えるというスタンスである様に見受けられた。2016/10/17
ひなた
2
★4 バランスの取れた良書。2015/02/11
-

- 洋書
- The Drawings
-
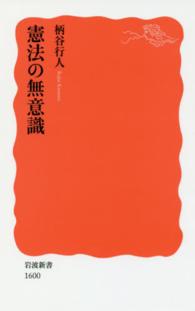
- 和書
- 憲法の無意識 岩波新書