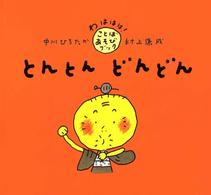出版社内容情報
「かな」は日本語を表わす独自の文字であり,その起源は平安初期の万葉がなに求めることができるという.しかし,「かな」がどうして出来上り,定着したか,その成立と変遷にはなお不明なところも多い.従来の研究を更に一歩進め,断簡零墨にいたるすべての資料を渉猟してその推移を追跡し,かなの成立と変遷とを明快に述べる.
内容説明
「かな」は日本語を表わす独自の文字であり、平安初期に万葉がなを起源に成立したという。しかし、「かな」がどうして出来上り、定着したか、その成立と変遷にはなお不明なところも多い。従来の研究を更に一歩進め、断簡零墨にいたるまで、すべての資料を渉猟してその推移を追跡し、かなの成立と変遷について明快に述べる。
目次
1 発生(漢字の渡来;漢字のはたらき;日本語の表記;『古事記』と宣命書き;落書きと、文字を理解した人々;万葉がな;万葉がなの遺品)
2 展開―かなのいろいろ(男手;草;女手;片かな;葦手)
3 定着―書としてのかな(平安時代の手習いとその詞;かなの消息;調度手本と『古今和歌集』)
著者等紹介
小松茂美[コマツシゲミ]
1925‐2010年、山口県岩国市生まれ。1942年山口県立柳井中学校卒業。東京国立博物館勤務、1986年より古筆学研究所を設立、主筆。その後センチュリー文化財団理事・館長を務める。専攻、古筆学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sabosashi
6
漢字は中国から取り入れられたもので、ニホンで独自に造り出されたのがひらがなとかたかなであることは、だれでも知っている。 そういうことを仕事柄、頻繁に話さなくてはならない。 しかし実際にひらがなはどの程度の割合で広がっていったのだろうか。 初めは貴族、それもおとこのみが文字(漢字)を操り、おんなは遠ざけられていたとか説明しているわけだが、ほんとにそうだろうか。 たとえば法隆寺の再建は八世紀の初めであるが、宮大工たちの落書き、つまり当時の歌謡が書き残してあるとかいう。 2014/09/25
澄川石狩掾
2
研究が進んだ現代からすると学説が古い部分もあるが(ワカタケル大王の漢字の当て方など)、古筆学の大家による入門書ということで、かなの成立までの歴史について勉強になった。2021/11/27
gorgeanalogue
2
通読したのは三度目くらい。どうもこの人の文体は好きになれないし、いろんな新資料が出ていて、学説は更新されているはずだし、またたとえば和歌技法とかな文字の関係なども書かれていない。さらに平安書道を至上のものとする態度から、鎌倉以降はろくに書かれていないなどの瑕瑾はあるが、それでもかなの歴史を概観するには、他にない入門書である。別にノートを取らないと、付箋ばかりが増えていく。2017/02/15
すんだ
1
<一言>タイトル通り、かなの成立から変遷・発展が流れるように著された書。個人的には、男手と真仮名、女手と平仮名など概念が重なり複雑ではあったが、それぞれの特性や芸術性に対する作者の深い理解があることは伝わってきた。分かるまで再読したい。<メモ>日本への漢字の伝来、定着、かなへの転換、各種の展開、芸術としてのかなの成立2016/10/12
-

- 洋書
- Identitä…