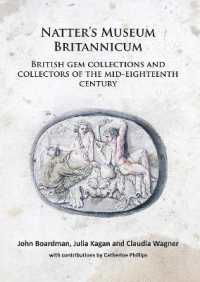感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
16
1970年初版。戦前の大正・昭和期の労働組合運動について、研究された本です。とくに友愛会の創設から解散、その後の労働組合の変遷について述べられています。この時代は、治安警察法や治安維持法などで労働運動をすることが困難であるばかりか、体制変革を主張すると弾圧される時代でもありました。そういう意味では労働組合運動にとって「暗い谷間」ではあったのだと思います。労働組合内部の論争や争いと、天皇制権力の弾圧とがどのように関わっていたのかを、もう少し詳しく分析されていたらよかったのにとは思いました。2015/06/06
スズツキ
3
入手困難だったが、今年になってひっそりと復刊してた。ロシア革命当時の日本の社会主義者たちの息吹がそのまま伝わってくる。1970年の本だが、その後社会主義がどういう運命を辿るのかを知っていると、やっぱり日本の停滞の原因はこの辺りだな、と思うわけです。2015/06/29
みかん
2
あまりに面白い本であった。悔しいことに中身については語るには力が足りないのであえて読みやすさだけ言及すると、端正で、リズムがよい文体に加えて、効果的に引用された当事者たちの論文や演説、自伝が当時の息づかいを伝える。最初から最後まで読者をとらえて離さない名著であった。…とにかく、思っているより読みやすいので百聞は一見に如かず、読んでいただきたいし、他の著作も復刊してほしい。2024/04/29
たけかず
0
友愛会(総同盟の前身)結成、総同盟の方向転換(山川論文の影響)、そして総同盟の分裂までの流れが面白い。総同盟において、アナ系(サンジカリズム系)とボルシェビキ系との対立があったのが、大杉栄亡き後後者が優勢になっていったこと、しかし、その後のボル系(評議会)の活動がまるでアナ系のような行動になっていったことはとても興味深い。親方=徒弟的人間関係の崩壊、そして「うちの従業員」の成立が、特殊日本的雇用(非横断的縦の労働市場)に影響してることの示唆も面白い。産業報告会が戦後の企業別組合の土台となったことも示唆的。2017/11/03
Ishida Satoshi
0
読了。古い本です、日本の労働運動における大正・昭和期における変遷を辿った内容です。治安維持法と日本独特の集団主義、組織内外での対立、定着を妨げられた「暗い谷間の時代」であったと語っています。世界恐慌や世界大戦の合間で、イデオロギー的な葛藤、分裂、衰退へと向かっていく労働運動が描かれています。戦争体制が確立する頃には、労働運動は骨抜きにされてしまっていくわけです。労働組合などが辿った戦争、ファシズム下での痛切な経験が、平和と民主主義を維持していくことの難しさを伝えている本でもあります。