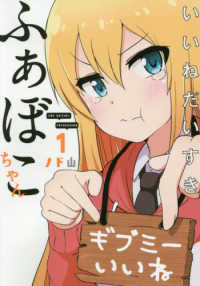出版社内容情報
古代から現代にいたるまでのわが日本の数学はどんなものであったか.また,なぜそうなったのか.本書は,この課題に対する答案である.和算は,わが国の学問の中でも最もよく日本人の独創性を発揮したものの一つである.世界科学史上に輝く和算や明治期の数学を,日本人の性格や社会文化との関連のもとに解明する.
内容説明
古代から現代にいたるまでのわが日本の数学はどんなものであったか。また、なぜそうなったのか。本書は、この課題に対する答案である。和算は、わが国の学問の中でも最もよく日本人の独創性を発揮したものの一つである。世界科学史上に輝く和算や明治期の数学を、日本人の性格や社会文化との関連のもとに解明する。
目次
第1日 和算のはじまり(この話の目的;戦国時代までの数学 ほか)
第2日 和算の発展(和算飛躍の時代的背景;筆算による代数の成立 ほか)
第3日 和算の成熟とその特色(和算の近代化へ;主な指導者 ほか)
第4日 和算の特色(つづき)と、洋算の輸入(和算家の生活と趣味;和算の論理、直観と帰納 ほか)
第5日 近代的数学の確立(明治初年の数学界;学制の影響 ほか)
著者等紹介
小倉金之助[オグラキンノスケ]
1885‐1962年。東京物理学校卒業。数学者、数学史家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
有沢翔治@文芸同人誌配布中
6
数学と言えばヨーロッパが本場だという印象があるかもしれません。しかし日本も数学は独自に発展してきました。本書は江戸時代を中心に和算の歴史を見ています。2017/02/19
ちくわん
5
小倉金之助、1940年(昭和15年)。江戸時代から明治維新までの「和算」が、「洋算」に取って代わられて廃れるまでを語る。当時の日本語の口語表現を文字化しているので、妙~な懐かしさを感じる。塵劫記までは順調な和算であったたが、一子相伝のギルド的な感じになり、とても学問とは呼べない、「芸」と断罪される。振り返って西洋の数学と和算を比べると、そういう評価もあるのか。印象的なのは『西洋』VS『日本』の西暦別、有名な数学者の対比表。このメンバーと比べれば(どこの時代のどの国でも絶対)負ける。2018/08/22
takao
1
8世紀の頃は、そろばんもなく、算木で計算(加減乗除、平方根、立方根、一次の連立方程式)した。負数も使われた。2017/02/10
松本佳彦
0
小倉金之助による、和算の興りから滅亡までの解説5日間。1939年のラジオ講座を翌年春に書籍化したもの! 心地よい語り口ながら、しばしば忌憚のない意見を述べるのがおもしろい。80年後の自分には和算について紋切り型の認識しかなかったことを実感させられた。和算は「芸」であったという原則的理解自体は、それは否定できないとしても、たとえば一種の積分法である「円理」は、ある時期の和算家が提出してそれで終わったわけではなくて、検討が重ねられて洗練されていったらしい。ちゃんと積み上げがあったんだ。2022/02/26
阿房門 王仁太郎(アボカド ワニタロウ)
0
科学が認識の体系であり神知ではない事が改めて窺える。小倉は和算の体系的な観点の無さ、他分野との没交渉、自己を権威にする余りの秘密主義を批判しているが、それは和算に限らずある種の科学に不可避の袋小路なのかもしれないと今の学閥だの文理の煽り合いだのに感じてしまう。科学は「遊び心」や「驚異」に耽溺しても離れすぎてもいけないのだろうし、そこ健全さは専門家以外の介入という「予測不能な可能性の介入」により成し遂げられる。学問は常に新たな可能性と自己否定と模倣でない自己研鑽を受け入れるべきだろう2021/09/15