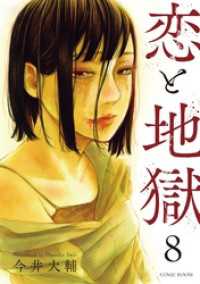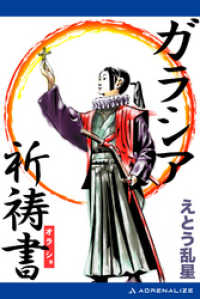出版社内容情報
哲学上の最重要問題の一つ〈心身問題〉にベルクソンが挑んだ第二主著の最新訳。精神と物質の二元論のアポリアをいかに打ち砕くのか。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
esop
78
村上春樹、海辺のカフカ?に登場した著作。 アンリベルクソンが、心身問題に取り組む。 心身2元論で行き詰まる問題を独自の提案で解き明かそうとする本著、必死についていこうとするが、難解でめちゃめちゃ置き去りにされる。1度読んだだけでは到底理解できない。だが、なんとなくこうかな?って自分なりに解釈できると楽しい。 面白いところ「記憶ってのは、現在→過去に逆行するもんじゃなくって、過去→現在に前進するところに成り立つもんだっ!」「脳ってのは記憶を保存するとこじゃくてさ、一種の電話交換局にすぎない」 再読必至2025/03/29
さきん
19
現在はさらに脳科学や神経医学が発達して当時とはまた違う解説になると思うが、感覚や記憶を単なる体内の物質のやりとりとして捉えるのみではなく、哲学と科学の間の解釈、どう観念、感覚として捉えるかということにこだわっているように感じた。とにかく読むのが大変。集中力が持たない。2016/08/24
呼戯人
18
ベルクソンの4大主著のうちの一つ。当時の失語症の研究などに基づきながらベルクソン自身の心理学を作っている。身体という特権的な物質と純粋記憶の中でまどろむ精神の関係を探っている。物質と精神が出会うのは、知覚によって捉えられるイマージュであるが、純粋記憶、記憶、イマージュ、知覚が一体となって、物質と精神が浸潤しあう。そこで物質と精神は一つのものになるのである。しかし、非常に難解でもう一度読む必要がありそう。次は小林秀雄の「感想」でも読みながら再読したい。2022/01/20
kinka
13
生きてるってどういうことか、と考える時、モノとしての肉体を見るか、観念としての精神を見るかっていうのが昔からの学問のやりかただったのだと思う。ベルクソンはどっちにも与しない。モノとモノじゃないものの統一を目指し、記憶と物質世界を行き来する「運動」が感覚であり、知性であり、生命なのだと言う。肉体の役割は、記憶と物質の中継局であり、ここで観念が現在に、夢が流れる時間に変化するのだ。これ、思考実験なんかじゃないよ、参照文献には大脳生理学や心理学や物理学の膨大なリスト。全部噛み砕いてものにしてる、凄いわ。2016/01/06
彩菜
10
私が何かを知覚する時、私の身体はその刺激を行動へと繰延る。この生まれつつある行動は私の精神的生・記憶に働きかけ、その知覚に類似した記憶を選び、知覚を補完し最も有用な行動を示唆する。私の心理学的生はこの知覚で合流する身体と記憶の両極で振動し、その時々の感覚-行動が作る生への注意とでも言うような精神の緊張に応じた観念を創り出す。だから私はある外国語からその国を、又その言葉を発した人をその時々で思い出すのだ。このように生と行動という方向から著者は身体と心の合一の道を辿り、それに伴う二元論にも解を与えてゆく。2018/12/29