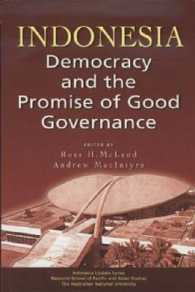出版社内容情報
現象に内在する精神とは? 精神のエコロジーとは? 科学と哲学をつなぐ基底的な知の探究を続けたベイトソンの集大成。その生涯にわたる思索の足取りをたどる。上巻はメタローグ・人類学篇。頭をほぐす父娘の対話から、隠喩と類比を信頼する思考の方法、集団間の緊張を高める「分裂生成」の型とそれを回避する「プラトー」の概念まで。
内容説明
現象に内在する精神とは?精神のエコロジーとは?科学と哲学をつなぐ基底的な知を求めたベイトソン。その生涯にわたる思索の足取りを辿る。上巻はメタローグ・人類学篇。頭をほぐす父娘の対話から、類比を信頼する思考法、分裂生成とプラトーの概念まで。(全三冊)
目次
序章 精神と秩序の科学
第1篇 メタローグ(物はなぜゴチャマゼになるのか;フランス人は、なぜ?;ゲームすること、マジメであること;知識の量を測ること;輪郭はなぜあるのか ほか)
第2篇 人類学研究における形式とパターン(文化接触と分裂生成;民族の観察データから私は何を考えたか;国民の士気と国民性;バリ―定常型社会の価値体系;プリミティヴな芸術のスタイルと優美と情報 ほか)
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Vakira
44
放っておくと物がゴチャマゼになるのはなぜ?普通かつ単純に娘さんの質問。それに対し父親の導き出した解。これって 僕を理系に導いたエントロピー増大の法則!初っ端から親子の会話に熱力学第二法則に出会えるとは思わなかた。そうか、熱力学第二法則は日常生活に普通に存在していたんだ。グレゴリー・ベイトソンさん 初読み。ていうか、この著者知らなかった。もう、40年前に亡くなった文化人類学者らしい。何で今頃?岩波文庫の新刊にこの本があり、表紙の画に惹かれ手に取り、中身拝見。ん?親子の対話形式の考察に惹きつけられ、即購入。2023/06/22
加納恭史
23
やはり「精神と自然」の一読では降参だな。続いてこの本で関連を見つけたいが、まだ当面は無理らしい。この本は生物学や文化人類学の本なのだが、私には馴染みがないし苦手なところだな。まあゆっくり目を通すしかないな。最初の父と娘の対話メタローグの話。娘は実の娘メアリー・キャサリン、父はベイトソン本人。二人とも文化人類学者。最初は「物はなぜゴチャマゼになるのか」。また「輪郭はなぜあるのか」。次第に哲学的に。ウイリアム・ブレイクの言葉、「賢人は輪郭を見るがゆえに輪郭を描く」。バレエの白鳥の湖では人間が白鳥のようになる。2025/04/07
∃.狂茶党
18
『精神と自然ー生きた世界の認識論ー』が、あまりに面白かったので、至急買ってきた本。三ヶ月かかったけど読み始め。 この文庫版は、元本を三分割したもので、短い論考を束ねた本だから、どこから読んでも良いとのこと。 実際関連する話題はあれど、章が変われば別の本のようでもある。 バリ島の文化人類学的記述が興味深い。 ここに綴られているようなこと、多分今は、破壊されているのだろうな。 んで、どうも、スルー予定だった、ゲームの理論に関する本も読まねばならないようようだ、まだ上巻だっていうのに。2025/10/10
roughfractus02
15
世界は生きている。安定は言語で分節した世界の捉え方であり、人間なる語も西洋ローカルの考えである。生物学、人類学、精神医学、生態学を渡る著者の40年弱に渡る論文を集めた本書(全3冊)は娘との7編の対話(メタローグ)から始まる。冒頭の対話では人間の分析・総合的世界構成が効かない動的世界を、ごちゃ混ぜなものは復元できないと逆問題から考え、人類学調査では他文化に西洋語のラベルを貼る際の思考のプロンプト場面を自らの失敗例で示す。その仮止め思考はバリ島でプラトー状態を見出していく(本巻は人類学領域の第2編まで収録)。2023/05/21
たかしくん。
13
いつかは読んでみたいと感じていたシリーズ。中々の骨太な内容です。上巻の半分を占める父と娘の会話ですが、面白いけど、油断するとすぐ取り残される。いわゆる思考法なるものを求められます。本巻の後半は、民俗意識、国民性の違いのルーツを探るべく、バリ島をはじめとする原始社会を例に出す。備忘として:エートスの定義として「個人の本能と情動を組織する、ぶんぁ的に平準化されたシステムの流れ」(p241)。他、英米をハイコンテクストと分類し、仏をローコンテクストと分類。2025/01/27
-
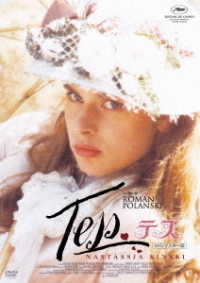
- DVD
- テス<4Kリマスター版>