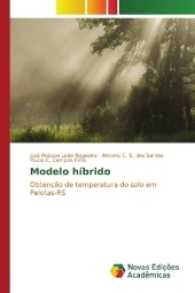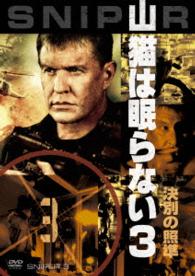内容説明
国家が市場に介入する後期資本主義の時代において、政治・行政システムが経済システムの危機に対処不能となり、大衆の忠誠を維持できなくなる「正統化の危機」。それは社会全体から統合の基盤が失われる現代特有の構造的な現象である。ルーマンとの論争を経て、諸システムにおける危機の連鎖を理論的に分析した1973年の著作。
目次
第1章 社会科学的な危機の概念(システムと生活世界;社会システムのいくつかの構成要素;社会の組織原理の例示;システム危機―自由主義的資本主義における危機循環を例とする解説)
第2章 後期資本主義における危機の傾向(後期資本主義の記述的なモデル;後期資本主義的成長から帰結する問題;ありうべき危機の傾向の分類;経済的な危機の定理について;合理性の危機の定理について;正統化の危機の定理について;動機づけの危機の定理について;回顧)
第3章 正統化問題の論理によせて(マックス・ヴェーバーの正統化の概念;実践的問題の真偽決定可能性;普遍化可能な利益の抑圧のモデル;個人の終焉?;複雑性とデモクラシー;理性に与する党派性)
1 ~ 1件/全1件