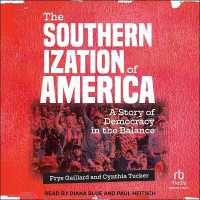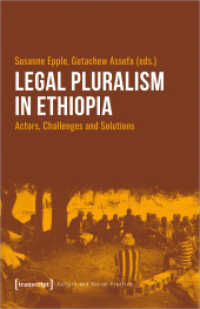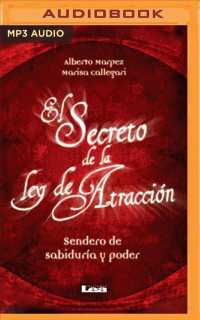出版社内容情報
壮大な〈世界システム論〉を唱えたウォーラーステイン(1930-2019)。資本主義をひとつの歴史的な社会システムとみなし、「中核/周辺」「ヘゲモニー」「帝国」「反システム運動」などの概念を用いて、その成立・機能・問題点を鋭く描き出す。現代世界を批判的に検討し、未来を展望するうえで示唆に富む位置一冊。
内容説明
壮大な“世界システム論”を唱えたウォーラーステイン(1930‐2019)。資本主義をひとつの歴史的な社会システムとみなし、「中核/周辺」「ヘゲモニー」「帝国」「反システム運動」などの概念を用いて、その成立・機能・問題点を鋭く描き出す。現代世界を批判的に検討し、未来を展望するうえで示唆に富む1冊。
目次
史的システムとしての資本主義(万物の商品化―資本の生産;資本蓄積の政治学―利益獲得競争;真理はアヘンである―合理主義と合理化;結論―進歩と移行について)
資本主義の文明(バランス・シート;将来の見通し)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
syaori
71
資本主義を一つの社会システムとみなし、その機能を検討してゆく本。資本主義とは「馬鹿げたシステム」だと作者は言う。この中で人は資本を蓄積するために資本を蓄積し、「中央のメカニズムがより効率的になって」搾取は強化され、その矛盾(富の両極化等)は普遍主義や合理主義が隠してきたのだと。また、地理的に拡大して安価な労働力を取り込むことで繁栄してきたこのシステムは、そのために「近代化」を強制しヒエラルキーを構成してきたのだという作者の評価の先に、分断とグローバル資本主義の歪みに喘ぐ現在の世界があるように思われました。2023/08/30
1.3manen
66
図書館新刊棚より。資本主義とは、史的な社会システム(19頁)。書名の史的システムとしての資本主義とは、生産活動を統合する場。時空の限定された具体的な存在(28頁)。反システム運動の強みのひとつは、多くの国で権力の座についたこと(113頁)。覇権であるヘゲモニーとは、中核を構成する強国でも一国の経済力が圧倒、商品が周辺や半周辺においてはもとより、他中核諸国でも競争力をもつ状態(115頁訳注(3))。文化帝国主義こそ、知的解放の名において支配し、懐疑主義において影響力を及ぼした(133頁)。デリンキングで思い2022/09/02
koji
27
ウォーラーステインが亡くなって3年。何となく読みたくなり手に取りました。原著は1984年、システムとしての資本主義の限界を描ききって、全く色褪せない見事な1冊。著者の歴史観「近代世界史ステム」は、長期の16世紀が資本主義的世界経済の形態を取って、欧米、ひいては地球規模の発展を促してきたが、そこに孕む個人主義の行き着く先は不平等を助長し危機を深刻化させるというもの。著者が提示する出口は3つ。①新封建主義、②民主的ファシズム、③高度に分権化され平等化された世界秩序。③を切望する著者の通りになるか、考え続けます2022/11/18
春ドーナツ
17
で二冊目。資本主義=民主主義。だっけか? そこから始めます。著者によると前者は16世紀ぐらいまで遡れる。後者はWikipediaを引用。「近代の政治思想上で初めて明確にデモクラシー要求を行ったのは、清教徒革命(1642~49)でのレヴェラーズであった」17世紀ね。資本主義はそもそも貧富の格差がどんどん拡大していく全世界を覆うシステムであると。XからYに政体を覆しても、大気圏のように突破することはできない。私たちの歴史が教えてくれます。サン=シモン主義が描くユートピアが建設されていたら、どうよ? と考える。2022/08/18
Ex libris 毒餃子
16
「世界システム理論」で有名なウォーラーステインということで読む。難しかった。2022/08/06
-
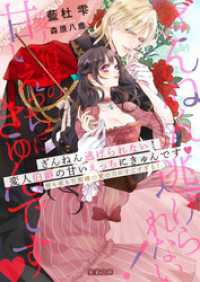
- 電子書籍
- ざんねん逃げられない!変人伯爵の甘いえ…