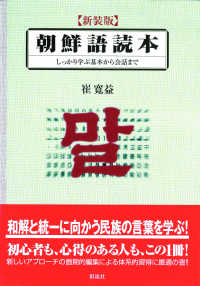内容説明
一九〇三年苦しいロンドン留学から帰国した漱石は帝大で教壇に立つ。後の文豪の世界文学との邂逅は近代日本に何をもたらしたか。一見難解な外観、厖大な引用、苦渋とユーモアの口調に漲る文学修行の精華。西洋と日本をつなぐ迫力満点の講義録。
目次
第1編 文学的内容の分類(文学的内容の形式;文学的内容の基本成分;文学的内容の分類及びその価値的等級)
第2編 文学的内容の数量的変化(Fの変化;fの変化;fに伴ふ幻惑;悲劇に対する場合)
第3編 文学的内容の特質(文学的Fと科学的Fとの比較一汎;文芸上の真と科学上の真)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Gotoran
41
1903年苦難の倫敦留学から帰った漱石が、東京帝大で英文学講師として留学時代に集めた数多の引用、苦渋、およびユーモアを交えて、”根本的に文学とはどのようなのものか”を論じたもの。本書上巻では、漱石文学論の要諦であるところの「F(Focus)+f(feeling)」の理論的基礎を留学時に集めた数多くの実例を交えながら解説していく。漱石文学論を実に興味深く読むことができた。引き続き、下巻へと進んでゆきたい。2023/03/18
ころこ
35
F(認識されるもの)とf(そこから感じられる情緒)という身も蓋も無いものに還元し、文学が人間に与える影響の普遍性を考察しています。脳科学者のように文学の終わりを文学の始まりにおいて宣告しているようにみえます。大きな問題に取り組み結果的に不発に終わった手ごたえの無さは、現在我々には科学と文学のフレームワークが見えるからです。本文では翻訳と日本語の問題、文語と口語の問題が生じています。つまり、ここでも日本語、英語、漢語と特殊なものが扱われ普遍性を追及していますが、混合した文章は更に我々の理解を遠ざけています。2020/12/24
shinano
12
明治の文語だから少し読み辛さはありますし、また漱石先生お得意の漢詩からの略語や禅語など、さすが漱石先生です。たくさんの外国書を読んでいることがわかります。英文学書にとどまらず英訳されている独仏露伊の書なども網羅している。先生のこの書による講義で、心理学と哲学の知識はやはり文学を創造するには必須の様に思いました。文学を創る側にも読む側にも『情緒』が一番大切だということですね、漱石先生。引用英文には英語力がないわたしには閉口でした。すみません、先生。2010/04/21
逆丸カツハ
11
流し読み。博学だ…。2024/03/31
yutaro sata
10
文学論がどうとかいうことよりも、漱石のこの時期の苦しさばかりが伝わってくるという感じがする。
-
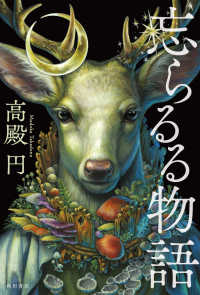
- 和書
- 忘らるる物語