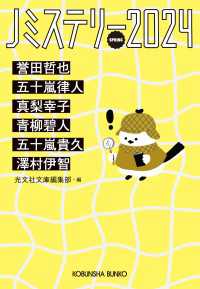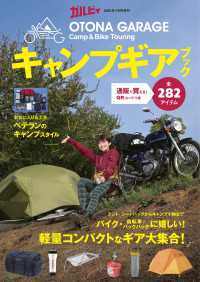内容説明
贈与や交換は、社会の中でどのような意味を担っているのか?モース(1872‐1950)は、ポリネシア、メラネシア、北米から古代のローマ、ヒンドゥー世界等、古今東西の贈与体系を比較し、すべてを贈与し蕩尽する「ポトラッチ」など、その全体的社会的性格に迫る。「トラキア人における古代的な契約形態」「ギフト、ギフト」の二篇と、詳しい注を付す。
目次
トラキア人における古代的な契約形態
ギフト、ギフト
贈与論―アルカイックな社会における交換の形態と理由(贈与について、とりわけ、贈り物に対してお返しをする義務について;贈り物を交換すること、および、贈り物に対してお返しをする義務(ポリネシア)
この体系の広がり。気前の良さ、名誉、貨幣
こうした諸原理の古代法および古代経済における残存
結論)
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
syaori
63
お歳暮等に代表される贈与。建前上は自発的、実際は贈る・受け取る・返すという義務から成る贈与の社会的な意味を探る本。作者は古今東西の贈与の体系を概観し、現代の資本・功利主義とは全く別の倫理を持つその体系に人間の「行動原理であり続けてきたもの」があると語ります。贈与とは、ある集団が異なる集団・人と、物を贈ることで連盟し、また物を贈ることで互いに優越しようとする装置で、剣ではなく財で友好と競合を体現することで様々な社会関係を安定化させてきた「連帯の不変の秘訣」。それは今日でも重要な意義を持つように思いました。2022/08/26
うえぽん
56
仏の社会学・民族学者が、約100年前に古今東西の贈与体系を法・経済・宗教を含む全体的な社会的現象として分析した書。米州や豪州等の諸部族間の競覇型の全体的給付による連盟関係をポトラッチと呼ぶが、そこには贈り物への返礼義務のほか、贈る義務、受け取る義務が存在。こういう「贈与=交換」の原理は、個人間契約、市場や貨幣の概念に到達していない社会に広く存在したとする。集団間で戦争や孤絶に代えて連盟や贈与を選んだとするが、昭和まで広く見られた贈答文化や、現下の世界貿易摩擦に想像を広げれば、人間の可能性と限界に迫れるか。2025/04/16
1.3manen
43
1921年初出。訳者解説によると、モースはラディカルに社会運動・政治運動に実践的にコミットした経験をもってもいた(488頁~)。ギフトには贈り物と毒と2つの意味を持つ(37頁)。人と人とを結びつける物の交換と贈与は、共通の観念基盤にもとづいておこなわれている(43頁)。けちんぼはいつだって贈り物をこわがる(58頁)。遅れた社会でお返しする義務があるのか(傍点61頁、私なりに意訳)。倫理と経済は諸社会においても恒常的、潜在的に機能しているのが認められる(63頁)。 2016/03/27
(haro-n)
38
未開社会といわれる社会に見られる法的・経済的等の総合システムとして全体的給付(贈与)の体系を示し、その実態や原理を扱った論文。具体的事象を論じる箇所は興味深く読めたが、結論に向かい大風呂敷を広げ過ぎの感があった。全体的給付の体系が社会全体を活性化させることから、それが現代社会の諸問題とどう結び付けて考えられるかという箇所の議論が雑で説得力に欠けた。各システムの背景やその功罪等、もう少し具体的検証が必要なのでは…。それでも、贈与の仕組みに注目し人間同士の普遍的な関係・心理を論じたその切り口は魅力的だと思う。2017/06/28
Toska
32
古典チャレンジ。あちこちで引用・紹介されているから何となく分かっているような気になってしまうけど、現物は恐ろしい歯ごたえ。それが古典の古典たる所以なのだろう。人に物を贈る⇔受け取るという行為は、不可避的に前者の後者に対する優位を意味する。それ故、受け取った側は従属を回避すべく必死で「お返し」を試みるもので、そうした心性は古今の文明社会に共通しているという。人間ってのは難儀な生き物なのだな。諸々の宗教が慈善や喜捨といった概念でこの関係を和らげようとしているのも分かる気がする。2025/04/30