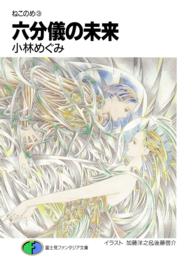出版社内容情報
北イスラエル王国,南ユダ王国において,前9世紀以来の列強の拡張戦争が始まった時期に現われた予言者たち.禍の予言が適中したことでその威信はゆるぎないものとなり,彼らの宗教思想はユダヤ宗教倫理を決定づけた.さらに,イスラエル国家体制の崩壊の後の,ユダヤ的パーリア民族の成立への過程が叙述される.
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
逆丸カツハ
39
理解したとは言い難いが目は通した。ユダヤ人も一枚岩であったわけでもなく、さまざまな階級の対立があったり、バール神とヤハウェの競争があったなど、背景にこんな歴史があったのだなぁ。しかし、ユダヤ教を理解するのは難しいだろうなぁ。生きている感覚が多分違いすぎる。2025/08/19
ヴェルナーの日記
5
主にユダヤ民族の捕囚前後~神殿破壊期を経て古代キリスト教の発生頃までをカバー。 ヴェーバーらしく社会学的思考から、古代ユダヤ教を解析し考察を加えている。 この頃のイスラム(北イスライム・南ユダ)王国は、バビロニア・ペルシャ帝国、エジプト・パロ(ファラオ)王朝という大国に挟まれ、北からアッシリアが侵入し(北イスライム滅亡)、挙句にバビロニアにおける神殿破壊よって、事実上ユダヤ民族は離散。その中で民族性を保ったのはユダヤ教の強固な結束性と排他性によるものだが、その排他的な要因がキリスト教の誕生へ向かう。2013/02/07
1.3manen
3
社会学的歴史叙述(1027ページ訳者解説)。合理的資本主義と非合理のそれが峻別。文化受容と文化の新創造との関わり(1069ページ)は興味深い。人生の、意味いかんを問う問題、苦悩と罪責とを負わされた破れやすい人生の無常性やその矛盾葛藤を正しく弁明すべき根拠は何か、インドで刺戟的な問い(752ページ)。現代日本でも人生のはかなさは鴨長明や吉田兼好から継承されていよう。「倒産、病気、不幸は、神の怒りのしるし」(875ページ)。イスラエルに限ったことでない。タルムードは聖書に次いでユダヤ人の基礎(913ページ)。2012/12/19
rynly
2
予言者が圧倒的存在感を示す巻。狂信的なまでの彼らの終末待望論が平民層に及ぼした影響ははかりしれない。旧約聖書の内的構造を規定し、それがキリスト教に流れ込み、さらには現代の西洋社会にまで及ぶほどのものであったとまでヴェーバーは言いきる。神への民族レベルでの徹底的帰依が、実践的には儀礼主義や律法主義へと転化していく様、破壊された政治団体が宗教団体として生き延びていく様、さらに生成しつつあるキリスト教と共鳴し、そして乖離していく辺りなども、ものすごくスリリングな展開でほんとにおもしろい。2014/04/01
Akiro OUED
1
イスラエルの王国の滅亡、捕囚時代を経て、ローマ帝国に組み込まれた。その間、多種多様な神に出会いつつ、ヤハウェを唯一神として堅持した。ユダヤ人と日本人の神への態度は対象的だ。異教徒を排除したユダヤ人が、逆に世界から排除されることになったのは皮肉だね。社会学的歴史叙述、面白かった。2023/07/09
-

- 洋書
- The Coward



![Pragmatics of African Varieties of English (Mouton Series in Pragmatics [MSP] 33) (2025. X, 332 S. 16 b/w ill., 25 b/w tbl. 230 mm)](../images/goods/ar/work/imgdatak/31115/3111567753.jpg)