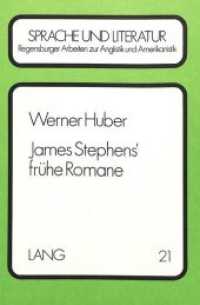出版社内容情報
第一次大戦後の混迷のドイツ.青年たちは事実のかわりに世界観を,認識のかわりに体験を,教師のかわりに指導者を欲した.学問と政策の峻別を説くこの名高い講演で,ウェーバーはこうした風潮を鍛えらるべき弱さだと批判し,「日々の仕事(ザッヘ)に帰れ」と彼らを叱咤する.それは聴衆に「脅かすような」印象を与えたという.
内容説明
第1次大戦後の混迷のドイツ。青年たちは事実のかわりに世界観を、認識のかわりに体験を、教師のかわりに指導者を欲した。学問と政策の峻別を説くこの名高い講演で、ウェーバー(1864‐1920)はこうした風潮を鍛えらるべき弱さだと批判し、「日々の仕事(ザッヘ)に帰れ」と彼らを叱咤する。それは聴衆に「脅かすような」印象を与えたという。
1 ~ 4件/全4件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ムッネニーク
138
5冊目『職業としての学問』(マックス・ウェーバー 著、尾高邦雄 訳、1936年7月 発行、1980年11月 改訳発行、岩波書店) 社会学者として名高いウェーバーが、1919年1月にミュンヘン大学で行った講演のテキスト。職業として学問に従事することを志す人間に対し、ドイツにおける職業としての学問の現状、そして学問に専心することへの心構えを説く。ナチ党成立の前年に行われた本講演。まだ自由の気風が独にあったのだ。 「いやしくも人間としての自覚のあるものにとって、情熱なしになしうるすべては、無価値だからである」2023/01/27
ベイス
90
「学ぶことの意義」は時代とともに変化している。かつては「人生の意義(ギリシャ哲学)」や「自然科学の証明(各種の新発見)」と直結していたため、目的がひとつではっきりしていた。では現代においては?近頃の若いもんは、いろいろ要求が多いがそのいずれも学問に求めるのは筋違いだよ、ここまではよくわかった(思いのほか平易な文で驚いた。訳が巧みなのだろう)。では、現代における意義は何なのか、その答えが弱かったかなぁと。なんとなく「枝分かれした真理と真理を俯瞰してみる力を養うこと」という輪郭は見えたが…2023/01/25
molysk
78
第一次世界大戦後のドイツ。混迷の時代の中で、指導者としての言葉を期待した学生たちに、ウェーバーが投げかけた言葉。学問にできることは何か。学問は人類の幸福に直結するものではなく、その目的は究極的には存在しない。学問は、世界はこうあるべきという姿を論じるものではない。学問の寄与は、世界がこうであると述べることと、各人の物事への立場の明確化を助けることである。各人は自己の運命を、自分で見極めねばならない。それはいたずらに待ちこがれて得られるものではなく、日々の仕事における要求に従うことで成し遂げられるものだ。2021/07/04
シローキイ
64
ドイツが降伏し、敗戦国になって間もない1919年。ヴェルサイユ条約によってドイツは混迷の渦中に飲まれていた。人々は既成概念への疑問が尽きず、救世主のような革命的指導者を欲していた。それは大学にも波及していた。本書は他ごとに耽って学問をなおざりにする人への警告だ。ウェーバーは強い口調で学問は探求であることを説く。そして、それに携わる教職員、学生に向って言う。淡々とやれと。前者には公平性、後者は学問への実直さを以てやれと。学校は指導者が立つ場所ではない。2017/03/15
s-kozy
61
「ブーメラン読書」、こういうことがあるんですね。冬休みで家に帰っていた娘が実家の本棚から「読みたい」と出してきた本。大学生以来の再読かな。物事の普遍性を捉えようと悩み、考えている世代の人達は一度向き合った方がいい本。そういう点で素晴らしい古典。2020/01/19
-
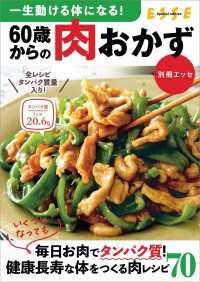
- 電子書籍
- 一生動ける体になる!60歳からの肉おか…