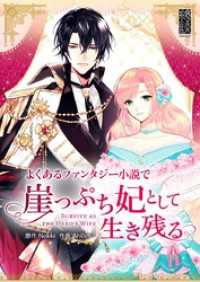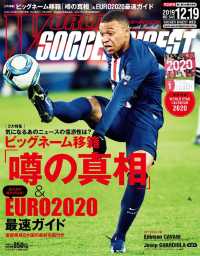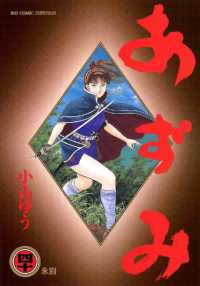出版社内容情報
営利の追求を敵視するピューリタニズムの経済倫理が実は近代資本主義の生誕に大きく貢献したのだという歴史の逆説を究明した画期的な論考.マックス・ヴェーバー(一八六四‐一九二〇)が生涯を賭けた広大な比較宗教社会学的研究の出発点を画す.旧版を全面改訳して一層読みやすく理解しやすくするとともに懇切な解説を付した.
内容説明
営利の追求を敵視するピューリタニズムの経済倫理が実は近代資本主義の生誕に大きく貢献したのだという歴史の逆説を究明した画期的な論考。マックス・ヴェーバー(1864‐1920)が生涯を賭けた広大な比較宗教社会学的研究の出発点を画す。旧版を全面改訳して一層読みやすく理解しやすくするとともに懇切な解説を付した。
目次
第1章 問題(信仰と社会層分化;資本主義の「精神」;ルッターの天職観念―研究の課題)
第2章 禁欲的プロテスタンティズムの天職倫理(世俗内的禁欲の宗教的諸基盤;禁欲と資本主義精神)
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ehirano1
130
いやいやいや、疲れましたwww。通称「プロ倫」。宗教と経済の関係を「天職(Beruf)」、「禁欲」、「予定説」の3つを以てウェバー大先生が説明されます。要は、なぜ宗教と資本主義が結びついたか?についてのウェバー大先生の興味深い回答です。古典として生き延びているので、その回答は広く支持されている一方、別の説も知りたいな、と思いました。2025/11/20
mukimi
114
普段は数冊並行で読むけど本書は一冊集中を要した。労働意欲や向上心について巷に様々な断言が溢れているが、歴史の中で多くの解が提示され試行錯誤されていることがわかる。私という一人の現代日本人にも思い当たる勤勉・倹約・自己審査の美徳は資本主義精神が海外から輸入されて根付いたもののなのか、凡ゆる人間の良く生きる知恵なのか、倹約と勤勉の実践が富と利潤の追求に繋がるという矛盾の中に自己顕示欲とか自己肯定感の探求が内包されてるのか、疑問が噴出したが、本書もあくまで一つの仮説を述べたにすぎない、との解説で一旦本を閉じる。2022/10/12
ひろき@巨人の肩
87
科学技術を基盤とする近代産業資本主義の原動力となったのは、禁欲的プロテスタンティズムの倫理観であったと因果関係を提示する本書。カルヴァンの予定説のもと、禁欲的労働による「世俗社会の修道院化」と、勤労成果としての利潤追求の隣人愛への転換を経て、資本主義は発展した。この逆説的な論理を鮮やかに説明しつつも、それがあくまで歴史的に見た因果関係であると控えめに主張している点に、マックス・ヴェーバーの凄さを感じる。資本主義精神の典型として、紹介されているベンジャミン・フランクリンの自伝は読んでみたい。2023/08/15
syaori
85
近代社会を覆う、資本の増加を義務とする精神。作者は、前の時代には卑しまれていたその精神が浸透する起源を古プロテスタンティズムに求め、ルターが聖書翻訳で日常労働に宗教的意義を認める「天職」概念を生み出し、それがピューリタン諸派の「恩恵の地位」を不断の職業労働によって確証しようとする心理と結びつき、「個々人の生活態度」を変える機動力となったことを詳述します。その後この宗教的部分は死滅して形骸だけが残るわけですが、「この巨大な発展が終わる時」にある今日この道筋を辿るのは、近代資本主義の寂寞たる葬送のようでした。2022/10/14
molysk
73
近代資本主義の精神の核心である世俗内的禁欲の思想は、プロテスタンティズムの宗教的禁欲の倫理に由来する。カルヴィニズムをはじめとする禁欲的プロテスタンティズムは、世俗における職業を神に召されたものとして、宗教的禁欲を世俗内的禁欲として確立させた。信徒は天職に励んで財を築くも、無駄な消費をせず、結果として蓄積された富は、近代資本主義の基盤となる。時が流れると信仰は薄れ、代わって金儲けが倫理的義務となる。こうして、反営利的な禁欲的プロテスタンティズムは、営利を目的とする資本主義の精神へと変わっていったのである。2021/05/02