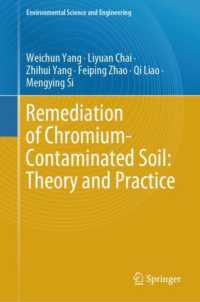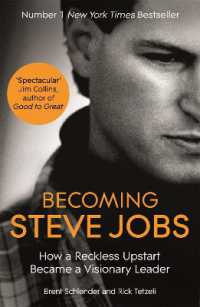出版社内容情報
『エコノミスト』編集長のウォルター・バジョット(一八二六―一八七七)は、一九世紀ロンドンの金融市場の実態をつぶさに観察し、金融危機の発生メカニズムと、その際にイングランド銀行が採るべき対応策について論じた。「最後の貸し手」としての中央銀行の行動規範、いわゆるバジョット・ルールを打ち立てた名著。改版。(解説=翁邦雄)
内容説明
金融危機が襲来!誰が何をすべきか。中央銀行の役割を描いた金融論の古典。80年ぶりに読みやすく改版。
目次
序論
ロンバード街の概観
ロンバード街はいかにして成立するに至ったかという事情と、なにゆえに現在の形態をとったかという理由
金融市場における大蔵大臣の地位
ロンバード街において貨幣の値が決定される方法
ロンバード街はなにゆえにしばしば甚しく鈍調を呈し、また時に極度に激発するかという理由
イングランド銀行が確実なる銀行支払準備金を保有し、これを有効に管理するというその職責を果たしてきたやり方に関する詳細なる説明
イングランド銀行の取締
株式銀行
個人銀行
ビル・ブローカー
イングランド銀行に保有されるべき支払準備金の額に対する調整の原理
結論
著者等紹介
バジョット,ウォルター[バジョット,ウォルター] [Bagehot,Walter]
『エコノミスト』編集長。1826‐77(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Bashlier
31
4/5 「元祖・金融危機論」19世紀エコノミスト誌編集者を務めた著者がイングランド銀行の役割について語った本書。中央銀行は金融危機の際、流動性供給により可能な限り商業銀行を支えるべきと熱烈に語ります。明確な”銀行を潰すべきでない”(Too big too fail)派。リーマンショックにより本著の正しさが証明され、今年のUBSによるCS救済に繋がっているように読み取れます。1873年の出版から丁度150年目に、巨大救済合併が起きたのは偶然なのでしょうか?歴史から学ぶ大切さを物語っているようです。2023/08/30
文
2
現代の金融政策に通じる理論が19世紀の時点で提唱されているのが面白い2024/11/10
ともちん
0
ウォルター・バジョットが1870年頃の金融危機の発生メカニズムと、その際にイングランド銀行が取るべき対策を説く。 銀行の最後の借り手は実質的にイングランド銀行な為、銀行支払準備金はどの程度に設定すべきか。その時の外国資本による債権がどの程度割合を占めているかによるため、一律には決められない。 イングランド銀行の総裁や副総裁、理事はどのような人間がなるべきか。名声が欲しいだけの有参加階級は総裁には不適合。有能で銀行業界に明るくなければならない。2025/07/27
どうろじ
0
19世紀の銀行の印象を知るにはちょうど良いだろう。なぜお金が銀行券を意味するようになったのか、中央銀行とは何か、信用とは?金利とは?為替とは?さらには筆者による理論家への批判もなかなか痛烈だ。制度が育まれるのは常に現実に起きた複雑な事情によるのであり、自然から単線的に発展して生まれるものではないのだ。2025/02/07
山崎 邦規
0
イギリスの金融を論じている。私として、金融の仕組みを十分に把握していないので、本書を通じて金融の畑を耕し、金融について語られた時のその内容について行けるようになれればいい、と考えて読んだ次第である。ある分野を知る上で、関連する本を多読することは、その分野の畑を耕すことであり、理解の度合いは少しずつ深まる。金融に関してはそこまで深く知ろうということではないが、一般教養程度に理解を持っていたいので、本書を呻吟しながら読み通した格好である。2024/12/08
-

- 電子書籍
- どうか君に暴かれたい【分冊版】 19 …
-
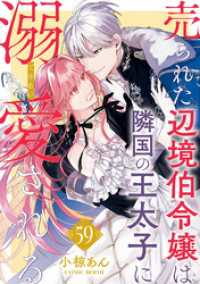
- 電子書籍
- 売られた辺境伯令嬢は隣国の王太子に溺愛…