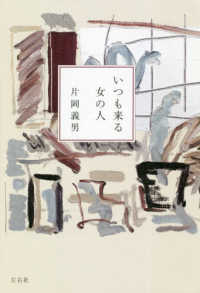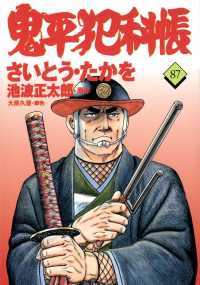出版社内容情報
19世紀のドイツ精神史に関する古典的著作。ヘーゲル思想の運命がマルクス、キルケゴール、ニーチェらの議論によって明らかになる。
内容説明
ヘーゲルの絶対精神の哲学を変革し逆転させたマルクスとキルケゴール。歴史的思考を永遠への憧憬によって転覆させたニーチェ。本書は19世紀のドイツ精神史に関する古典的著作。上巻ではヘーゲルからニーチェにかけて歴史がどのように哲学的に理解され、ありうる未来に向けて捉えられているのかという問いをめぐる議論が展開される。
目次
第1部 十九世紀における精神の歴史(ゲーテとヘーゲル)
時代の精神的潮流の起源―ヘーゲルの精神の歴史哲学から見る(ヘーゲルにおける世界史と精神史の完成―歴史の終結;老年ヘーゲル派、青年ヘーゲル派、新ヘーゲル派;マルクスとキルケゴールの決断―ヘーゲル的媒介の解体)
歴史的時間の哲学から永遠性の希求へ(われわれの時代および永遠性の哲学者ニーチェ;時代の精神と永遠性への問い)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
春ドーナツ
13
キルケゴール「不安の概念」の翻訳者はあとがきのおわりで、東北帝国大学の恩師であるレーヴィットに感謝を捧げている。戦前戦中の日本の思想界は、本書の著者から独立した思索を発展させたグループ(西田ほか)と上記の訳者のように影響を受けたものたちとに分かれる(そうです)。*ヘーゲルの哲学史を紐解いたので、自然とヘーゲルが含まれた哲学史も読んでみたくなる。ヘーゲル哲学の影響の射程の広さ、深さ、彼の没後に台頭した右派、左派、新ヘーゲル主義の流れが個人的に何となくつかめる。著者はゲーテを重要視していて「そうか」と首肯する2024/01/16
さえきかずひこ
13
ヘーゲル哲学を様々なヘーゲル批判から影絵のように浮かび上がらせる手法。それがはらむクリティクの豊饒さがとてつもない。ヘーゲルの存在の大きさが批判の数々から逆説的に照らし出されているのもまた確か。ヘーゲル左派、キルケゴール、そしてマルクスの哲学がその中心だが、P.470〜471にかけてナチスにおけるニーチェ受容の歪さを指摘するところはとりわけ鋭く、1941年時点での明晰な分析に驚かされる。またP.488〜489にかけてのハイデガー『存在と時間』について"神なき神学"とするのにも得心。ぜひ読みましょう!!!!2018/07/07
K
8
想像していたよりも読みやすい語り口で割とすいすい読んでしまった。正直理解が及ばない所も多々あったが、(タイトルにある通り)ヘーゲルからニーチェまでにおける19世紀のドイツ思想史を知る上で非常にありがたい著作だった。ヘーゲルにおける弁証法的考え方の様々な側面を後継者らは批判ないし継承するわけだが、本書でもある程度紹介されているように、完全には乗り越えられていないというか、そもそもヘーゲルの出発点に戻っている感じが否めない批判もあると思う。色んな思想を通じて「お前はどう思うのか」を突き付けられる感じでよい。2024/05/13
roughfractus02
8
カント『判断力批判』に形而上学からの自由を読むゲーテとヘーゲルは、以後別の道を歩む。経験と共にある事象(色彩環、形態システム)を探求するゲーテに対し、主体と事象の関係を経験の外(精神)に見出すヘーゲルは、キリスト教的な対立と宥和のシステムを人間を中心とした知の基盤に据え、歴史や近代の大学の知の構造を枠付けた。この構造が市民社会の基盤となり、後に育つ思想家達の論争のベースとなる。一方本書は、このキリスト教的二項システムから逸脱するゲーテの思考を、異教的な多元的ネットワークと捉え、自由の系譜に新たな線を引く。2021/10/08
Happy Like a Honeybee
7
瞬間は一切の永遠を体現する代表者(ゲーテ) シュヴァイツァー曰く、ヘーゲルとゲーテの思想とは集団主義か個人主義の闘い。 ドイツ精神史の学習に。 アーノルトルーゲやブルーノバウアーなど、手にしない学者の記述まで多岐に渡る。 消費とは共同の人間的活動の歴史的産物。 リンゴと言えども、交易と世界貿易の結実であり、決して直接には入手し得ない。 現実とは思惟と存在の仮説的な抽象的統一性の間に入って存在すること。 つまり関心を抱くことだ(キルケゴール)2017/12/27