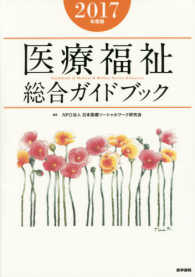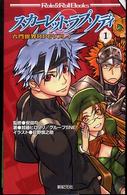出版社内容情報
19世紀フランスの形而上学者ラヴェッソン(1813‐1900),若くしてアリストテレスを自らの血肉とし,深くレオナルドの芸術に学んだこの高雅な思想家は,精神の伝統を堅く守って静かに一世を指導した.「習慣論」は題名の謙虚さにも似ず,実に自然と精神の全体を貫く天才的思索の結晶である.習慣の理解を通じて成り立った全存在の解釈である.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヒダン
10
習慣論+ベルグソンによる講演「ラヴェッソンの生涯と著作」の二本立て。前者は習慣という実践的なものをどうしてこんなに難しく論じてしまうのかとも思ってしまったけれど、深くて大きいことを表現するために必要だと読み進めてなんとなく理解した。旧字体がたくさん使われていて序盤の定義を理解しきれなかったのが課題。アリストテレスを読んでからいつか再読したい。一方で後者はビックリするくらい引き込まれる文章だった。説明的な文章にもかかわらず、例を挙げるのが上手いからか、ラヴェッソン本人が魅力的だからか、とにかく楽しく読める。2015/06/28
雁林院溟齋居士(雁林)
3
「習慣は第二の自然である」19世紀フランスの哲学者ラヴェッソンの主著。短いながらも大変内容の濃い書物であるし、やや後世の巨匠ベルクソンとの近親性があちこちに散見される。精神と身体、有機と無機、能動と受動を繋ぐ形而上学的な概念として、内面性として形成され、恒常性と変化を同時に有する第二の自然、習慣が論じられる。習慣とは、意志と自然の中項である。第一の自然をもこの習慣の方からのみ解き明かせると説いているのが又面白い。他にぱっと見て特に面白いのは努力の概念と、時間を意識の成立要件として説いてるところか。2012/11/02
hryk
0
「第二の自然」である習慣を解明するためには機械論哲学ではなく、アリストテレス主義とカント哲学のあわせ技でもある生命の哲学が必要であると説き、習慣からこそ生命が理解できるとも説く。無機物から生命への展開はヘーゲルの影響もあるだろう。ベルグソンの「ラヴェッソンの生涯と著作」も見事。2022/11/04
-

- 和書
- 立地論読本 〈2〉