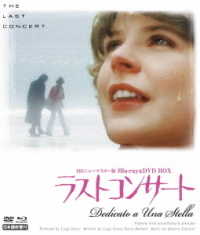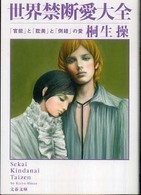出版社内容情報
科学的な方法による宗教心理学の最初の労作として不朽の名著.宗教を異常な精神現象のうち最高のものと見なす著者は,「健全な心」と「病める魂」の二つの傾向をあげ,両者における宗教的態度を多くの人々の厳粛な経験に照らして観察し,回心,聖徳,神秘主義などの現象を究明する.一九○一―二年のギフォード講義の記録.
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
70
(前略)本書は、要約したらつまらない。まさに多くの宗教的経験、体験の事例集の一面があり、そうした数々には、直接触れてもらうしかないのだから。 下手すると、何か狂気の世界に踏み込んでしまいそうになるし、そうでなくても、現代は、キルケゴールではないが、水平化、平面化、天上もなければ、地下もない、つまり高貴なる世界も仰がなければ、深遠の深みに畏怖することも避ける、そんな賢明なる常識人の世界なのだ。2009/08/26
かわうそ
38
『私は諸君におたずねしたい。精神史上の事実をこのように存在という観念から説明することで、その事実のもつ精神的意義をいったいどうして決定できるのか、と。』30 ジェームズ好きだなあ。そうそう客体を解き明かしても主体たる我々の精神が何か解明されるわけではない。『ある思想に善であるという刻印を押すのものは、その思想に含まれる内的幸福という性質である。』32 世界の原因の解明によって宗教が貶されることは決してないと言える。我々は個人的宗教を持つことで内的幸福がもたらされるならぜひ持つべきだ。現代に復活すべき幸福論2024/10/03
かわうそ
38
ジェイムズって相当にバークリーの影響受けてる気がします。知覚と存在。知覚されないものは存在しない。それってプラグマティズムに近くない?って話。2024/02/26
buuupuuu
20
ストア派は耐えるように人生を受け入れるが、宗教は喜びをもって受け入れる。この違いを成り立たせている心的経験はどのようなものか。上巻では、実在感、善いものだけに集中しようとする態度、逆に悪いものから目が離せなくなる性格、回心とは潜在意識下で進行していた統合過程が表面化したものだとする解釈などが論じられる。意見の価値はその起源ではなく効果によって測られるべきだというプラグマティズムや、人間の経験は多元的であるという見解など、ジェイムズ特有の思想も披露されている。手記などの引用が多数なされていて読みやすい。2024/03/08
Uncle.Tom
18
この本を読み返すたびに、宗教を排斥してしまってはいけないと感じる。人間にはおそらく秘められた超自然的な状態というものがあるのだろう。そのような状態に至るためには過酷な道筋を通っていかなければならない。その道標となるのが宗教である。逆に言えば、そのような状態に至れるのであれば必ずしも宗教が必要なわけではないが‥。人が死ぬほどの絶望を感じ、生きる意味をなくし、人生を諦めようと思った時。そんなある種諦めともいえるような境地に至った時に初めて、人は新たなステージへと進むことができる。2度生まれというやつだ。2020/05/14
-
![[正しい性聖書]形式結婚 新装版 15 SMART COMICS](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1930229.jpg)
- 電子書籍
- [正しい性聖書]形式結婚 新装版 15…
-
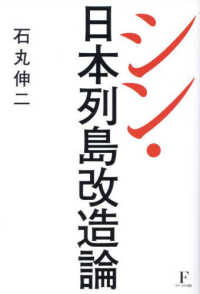
- 和書
- シン・日本列島改造論