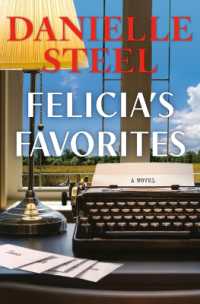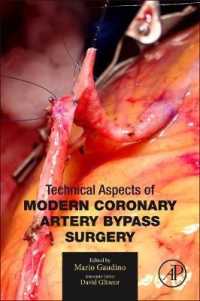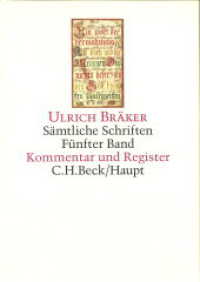出版社内容情報
ニーチェはキリスト教的道徳のもとに,また民主主義政治のもとに「畜群」として生きつづけようとする人々に鉄槌を下す.彼にとって人間を平等化,矮小化して「畜群人間」に堕せしめるのはこれら既成の秩序や道徳であり,本来の哲学の課題は,まさにこの秩序・道徳に対する反対運動の提起でなければならなかった.一八八六年.
内容説明
ニーチェ(1844‐1900)はキリスト教的道徳のもとに、また民主主義政治のもとに「畜群」として生きつづけようとする人々に鉄槌を下す。彼にとって人間を平等化、矮小化して「畜群人間」に堕せしめるのはこれら既成の秩序や道徳であり、本来の哲学の課題は、まさにこの秩序・道徳に対する反対運動の提起でなければならなかった。
目次
第1章 哲学者たちの先入見について
第2章 自由な精神
第3章 宗教的なもの
第4章 箴言と間奏
第5章 道徳の自然誌のために
第6章 われら学者たち
第7章 われわれの徳
第8章 民族と祖国
第9章 高貴とは何か
高き山々より―後歌
-

- DVD
- ちょこッとSister 第3巻