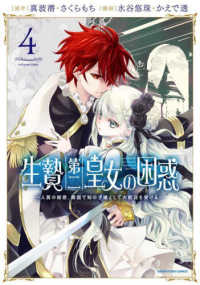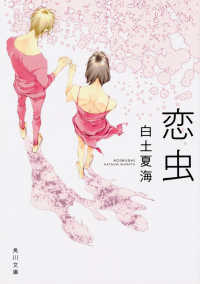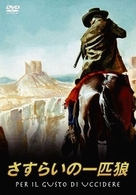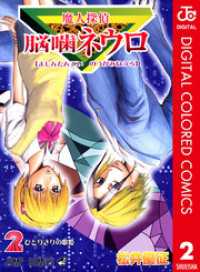出版社内容情報
ディルタイの芸術観を集約する代表的論文集で,一八九二年に発表された.近代美学における十七,十八,十九世紀の三期の特徴を明解に跡づけて,その歴史的帰結から当時における美学の課題を明らかにしようとする.特に,自然主義が果たした歴史的役割を重視してその将来性を強調,示唆するところは大きい.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ex libris 毒餃子
6
美学の知識が無さ過ぎて難しかった。2021/09/02
Nemorální lid
6
『審美的思索を長養して芸術と批評と議論好きな公衆との間に本然の関係を回復すること』(p.7)を目的としたディルタイの美学史であるが、『新しい芸術の根本特徴は下から上へであり、それはどの芸術も現実と、その芸術の働く際の夫々特徴や媒介の性質とに一層鞏固にどっしりと基礎を置いているところに存する』(p.10)ように、ただ絵画だけではなく小説や音楽などの普遍的芸術を対象としているのが面白い。そうした芸術品の意義は『我々の感性を満足せしめ、心を寛やかにする』(p.61)ためであり、価値はこうした判断に拠るのだろう。2019/01/04
ダイキ
1
「作家は科学から学ぶ。作家は如何なる現実の真にも背こうとしてはならない。といってしかし決して通俗的な自然科学の著述などに欺かれてはならなかった筈だ。芸術の天才が芸術の眼を以てじっくりと、真摯に、不断に人生と対晤するならば、ダンテやシェークスピアやゲーテの如く、如何なる生理学や心理学の書物よりも深く人生を認識するであろう。そうすれば現代文学の中に彷徨しこれを甚だしく陰惨にしている灰色の怪物、人間獣性の説も文学からその姿を消すであろう」〈現代の芸術〉2017/03/04
check mate
0
ディルタイの(1890年前後の)芸術観・人間観が僅々80頁の中に凝縮されている。天才の天才たる所以であるとか自然主義論などが特に興味深い。最後に謎のゲルマン礼讚で締められるのもまた興味深い(?)2015/09/04
be-
0
1960年発行ということもあり、仮名遣いは古く、また、そもそも内容が抽象的なものであるかつ書き手側から多くの教養を求められておりきちんと理解するためには読み手の努力を必要とする本。こちらのトピックに関する関心がそれほど強くなくモチベーションが起こらなかったため、さらさらとななめ読みするだけで終わりとした。2021/10/18