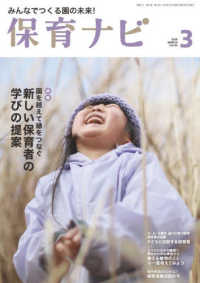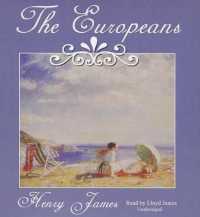出版社内容情報
「死に至る病」とは絶望のことである.本書はキェルケゴールが絶望の暗黒面を心理学的に掘りさげつつ,人間というものの本質を激しく追求したものであるが,繊細深刻をきわめる絶望者の心理描写の中には,多分に著者自身の自己分析と自己告白とが含まれている.ここに著者の哲学的思索の根本的な特色がある.
内容説明
「死に至る病」とは絶望のことである。憂愁孤独の哲学者キェルケゴール(1813‐55)は、絶望におちいった人間の心理を奥ふかいひだにまで分けいって考察する。読者はここに人間精神の柔軟な探索者、無類の人間通の手を感じるであろう。後にくる実存哲学への道をひらいた歴史的著作でもある。
目次
第1編 死に至る病とは絶望のことである。(絶望が死に至る病であるということ。;この病(絶望)の普遍性。
この病(絶望)の諸形態。)
第2編 絶望は罪である。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
69
宗教学の授業でこの本が取り上げられていました。キェルケゴールは貧しき境遇から神を呪って商売に精を出し、最初の妻が死んでからキェルケゴールの母に暴行を加え、妊娠させた父の罪に自分にも連なる絶望を見出していたという。幸福を甘受できる裏には深い絶望があり、その絶望から逃れるには自らが確固たる神への信仰を持たなければならない。だが私は人間は希望を知り、他人の幸福を推測できる理性があるからこそ、拷問や見せしめとしての虐殺など、他人を最も絶望に叩き落すことができる生き物だと思っている。そこにキリスト教の慈しみはあるか2014/08/29
やいっち
65
高校2年からキルケゴールに嵌まり出したっけ。キルケゴールにショーペンハウエルに、ニーチェに、ドストエフスキーにカフカにヴィトゲンシュタインにパスカルにベルクソンに埴谷雄高にフロイトにサルトルに。学生時代はドツボから抜け出せなくなった。ガルシンやらユングやらゴーゴリなどなど。ゴンチャロフなんかに学生時代遭遇しなくてよかったよ。オブローモフなんて二十歳前後に読んだらアウトだったかも。セリーヌも学生には禁書だよな。夜の果ての果てまで吹き飛んじゃう。荒野の狼に喰われてたか。魔の山で労咳に臥していたか。
かわうそ
56
人間は死ねない故に絶望する。自己自身を抜け出せない故に絶望するのです。絶望するのは過去が原因なのではなく現在において流れている時の一瞬、一瞬それ自体に絶望していることから生まれるのです。また、理想の自分になれなかったことに絶望しているのではなくて自分自身に絶望している状態を絶望というのであって、何か欲したものを手に入れなかったという理由で絶望しているわけではないのです。そして、自分を措定した力から引き離そうとする努力は報われず、その自己から逃れられない。死というのは絶望ではないのです。絶望とは死の消滅です2022/12/12
1.3manen
44
絶望は死に至る病(25頁)。 逆は、 希望は命に至る健康か? 玄田有史教授の希望学ではないが、 逆に考えてみればよいかもしれない。 絶望とは 自己自身を(傍点)食い尽すこと(27頁)。 ならば、 希望とは、自己自身を活かすことか。 想像力は無限化するところの反省である(46頁)。 他者に対する想像力の欠如は、 反省のなさに起因しよう。 無限性の欠乏は絶望せる固陋性、偏狭性である(50頁) 。2014/04/11
紫陽花と雨
40
正直に書きます。読み終わるのに4ヶ月もかかった…最強睡眠本(笑)絶望について超細分化して語られてる…細かく書かれすぎて「ごめん!キェルケゴール先生、何言ってるか分からない!」と何度なったことか…。あと時代のせいか、女性軽視が強い印象。最後は意地と根性で読み切りました。印象に残ったのは、キルケ=教会・ゴール=庭、で教会の庭に住んでる一家のあだ名で、お父さんがそれじゃあってeを足してキェルケゴールとしたって解説と、読了後の半端ない達成感。何も残ってないのにやり遂げた感じ…(笑)こんなレビューでスミマセン。2020/04/29
-

- 電子書籍
- 異世界サムライ【分冊版】 10 MFC