出版社内容情報
ヒュームがもっとも脂ののりきった時期に著わしたエッセイ集.勢力均衡・王位継承・理想共和国などを論じた政治論と,商業・貨幣・利子・貿易・租税などをめぐる経済論とからなる.いずれのエッセイも政治・社会・歴史に対する鋭利な洞察の結実であり,社会的現実を最高の関心事とする近代的哲学のあり方を示している.
-
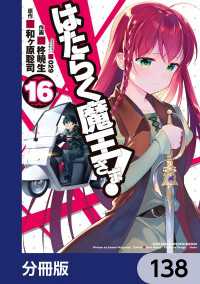
- 電子書籍
- はたらく魔王さま!【分冊版】 138 …
-
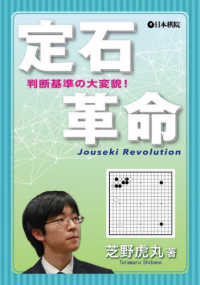
- 和書
- 定石革命




